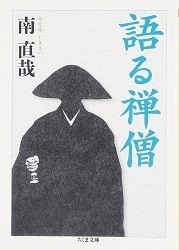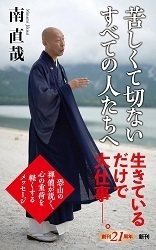こんばんは。
久しぶりに南直哉さんの本を読みました。
南直哉さんは曹洞宗の僧侶です。会社員の身から一念発起して出家。曹洞宗の大本山である永平寺にて約20年間修行し、2005年からは青森県の恐山菩提寺の院代を務めています。
このブログの最初の記事は2010年2月付ですので、今年で15年を迎えることになります。南直哉さんの本との出会いは、ブログを始めて2ヶ月後でした。その本は、脳科学者の茂木健一郎さんとの対談本、「人は死ぬから生きられる」でした。当時は茂木さんの本にはまっていて、その一環で読んだ本なのですが、茂木さんは直哉さんと対談するためにわざわざ恐山に足を運び、この対談を行って本として上梓したのです。
この対談で直哉さんは、仏教の教えや禅の心得などではなく、自らのフィルターを通して考え抜いた生き方や人への接し方、物事の考え方など、常識にとらわれない形で語っており、その語りは眼からうろこが落ちるようでした。
この対談で直哉さんの語りに魅了され、すぐにちくま文庫から発売されている「語る禅僧」という本を読みました。この本の面白さは、2011年2月13日のブログで紹介したとおりです。僧侶というと、法要のときに読経したあとに行われる説法を思い出して、その説教臭さに辟易しとした記憶がよぎりますが、直哉さんの本には説教くささは皆無です。
(文庫版「語る禅僧」 amazon.co.jp)
今回手にした本は、これまでになく変ったタイトルです。
「苦しくて切ないすべての人たちへ」
(南直哉著 新潮新書 2024年)
【ワンダーに響く言葉とは】
このブログを書いていて、いつも思うのは「言葉」の選択の難しさです。
直哉さんは、その語りの中で「言葉」の役割について、仏教を考え、伝えるための重要な手段だとしていますが、「言葉」は人と人をつなぐ手段でもあります。
これまでも直哉さんは、その著作で自ら歩んできた道のりを語っていますが、この本ではこれまで語られなかった過去も語られています。それは、直哉さんの言葉がどのように形作られてきたかを物語るワンダーを秘めています。
例えば、学生時代。大学生だった直哉さんは、ほとんど学校に行かず、下宿に「ひきこも」っていたといいます。その頃の毎日は、午前10時頃に起きてパンの耳をかじり、道元禅師の「正法眼蔵」とハイデガーの「存在と時間」を読みふけり、午後4時頃から銭湯での湯浴みと外食、それから帰って哲学・思想関係の本を乱読しながら明け方まで妄想とメモ書き、というものだったと書いています。
直哉さんは、「なぜ自分が生まれてきたのか」、「自分はなぜ存在しているのか」、この答えを知りたいとの欲求が昂じて、ついには出家してしまったという過去を持ちます。さらに、永平寺での修行によって精進し、数千年の歴史を持つ仏教思想を掻き込むようにして学んだのだと思います。直哉さんの本を読むと、彼の学んだ仏教は決して机上の理屈ではなく、毎日の毎時の毎分の毎秒の実践によって経験してきたものなのだと想像できます。
こうした経験を積んできた直哉さんは、「言葉」の持つ重要性とあやうさを良く知っています。
(単行本「超越と実在」 amazon.co.jp)
この本にあるエピソードですが、「宗教対話」の実践としてある会議に訪れたとある神父との話。会議後に雑談をしている中で、話の最後に神父は、「結局、仏教は神の存在を認めないのですね。」と問いかけます。直哉さんの答えは、「いいえ、単に必要がないのです。」
また、禅の修行にきたキリスト教の修道女が修行をして曰く、「あなたの説明によると、座禅とは石になるのと変らないのではありませんか。」答えて曰く、「それではいけませんか?石と人間と何が違うのですか。」、「人間には心があります。」
直哉さんの返事は、「石に心がないとどうしてわかったのですか?」
この話は、第三章の「真理」への欲望の項に出てくる話ですが、「言葉」の持つ諸刃の性質を良く物語っています。この本には、そんな直哉さんのワンダーな言葉がすべての話に秘められているのです。
【「一切皆苦」とは何か】
ところで、第44代アメリカ大統領となったドナルド・トランプ氏ですが、ロシアの侵攻から丸3年となるウクライナ戦争の停戦交渉に意欲を示しています。
この戦争で、ロシアは2014年に一方的にクリミア半島を占領し、さらに2022年2月にはウクライナの東側の領土に侵攻して、現在東部と南部の州を事実上統治下におき、さらなる侵攻を続けています。ロシア側の兵士の死者は9万5000人以上、ウクライナ軍の死者は4万5000人以上になると言います。あまつさえ、ロシア軍の攻撃によるウクライナ民間人の死者は、659人の子供を含め1万2000人以上に登ると言われています。
ウクライナとの国境を侵して侵略を開始したのはプーチン大統領であり、これだけの無垢な命を死に追いやったのはロシア側です。こうした事実を無視して、トランプ大統領は被害者であるウクライナのゼレンスキー大統領を無視してロシアと和平交渉を進めようとしています。
話を整理すると、まずトランプ大統領は、ウクライナに対してアメリカが支援した10兆円の武器や資金に対して見返りを要求しました。それは、ウクライナ領土に眠るレアメタルなどの鉱物資源を対価として提供しろ、という要求です。ゼレンスキー大統領は、アメリカとの関係を良好に保つため鉱物資源地図を提供したものの、採掘協定に関しては協定内にウクライナの安全保障に関する条項がないことを理由に保留しました。
すべての政策をディール(取引)と考えているトランプ大統領にとって、このことはよほど腹に据えかねたと見え、ロシア寄りの発言を連発するようになりました。
「プーチンが望めば、ロシアはウクライナ全土を占領できる。」
「ゼレンスキー大統領の支持率は4%だ。(実際は57%)」
「ゼレンスキー大統領は選挙なき独裁者だ。」
ウクライナ抜きの停戦交渉の開始をはじめとしたこうした一連の発言は、多くの罪なき死者やその家族を冒瀆し、戦争を是認する非人道的な発言であるとともに、ウクライナ市民の悲しみをさらに深いものへと追いやります。
今日、ゼレンスキー大統領はアメリカに行き、トランプ大統領と面談し鉱物資源採掘権の協定を締結するものとみられています。その動きがわかったとたん、トランプ大統領は「独裁者」発言を、「そんなことを言ったとは信じられない。」と知らぬ存ぜぬを決め込みました。これだけの人類史上の悲劇に対して、ディールと同等に相対するそのメンタリティーは人とは思えません。
(「信じられない」発言 sankei.comより)
こうした悲劇を見ると、ブッタの教えにある「一切皆苦」という言葉には真実が含まれるように思えます。今の日本は平和が続く幸せな国ですが、ここでも非正規労働者問題や母子家庭問題、ヤングケアラーの問題など、人生の喜怒哀楽はすべて「苦」に通じているというブッタの言葉には頷かざるを得ません。
この本の題名「苦しく切ないすべての人たちへ」には、ブッタの教えが反映されているのです。
【苦労話は自慢話?】
この本は、ある雑誌に連載されていたエッセイを本にまとめて上梓されたものですが、連載当時の表題は「坊さんらしく、ない。」だったそうです。
この本の目次を見ると、確かにその言葉が見受けられます。
はじめに
直哉さんの本がワンダーなのは、仏教の話にもかかわらず、そこに説法くささが微塵も感じられないところにあります。しかし、当のご本人は、「そろそろ、まじめに仏教のことを書いたらどうか。」という人からの助言に対して、「冗談ではない!私は最初から仏教の話を書いている。」と憤っています。
その理由は、直哉さんが仏教学者や宗教家とは異なり、すべてを自らの経験と言葉で書いていることにあるのではないでしょうか。
(「苦しくて切ないすべての人たちへ」 amazon.co.jp)
まさに第三章には、この話が出てきます。直哉さんは、3歳の時に小児ぜんそくを悪化させ、いつ窒息死してもおかしくない押し迫った危機感が身についてしまったと言います。そして、自らの生死を考えるために仏門に入ってからも、「諸行無常」や「無我」、「縁起」という言葉が研究対象ではなく、そのものが自らを表す言葉だった、そうなのです。
ある人は氏の本を読んで、「君は仏教で自分語りをした草分けだね。」と言ったそうですが、その言葉は直哉さんのエッセイの本質を言い当てているのかもしれません。さらに直哉さんの語りがワンダーなのには、ある教訓が生きているからなのです。それは、父親が語っていたという言葉でした。「他人の自慢話は誰も聞きたくないだろう?苦労話は自慢話と同じだ。どうしてもしなければならないときは、笑い話にして言え。」 なるほどナア。
【目から鱗のワンダー】
さて、この本の最後の章には、目から鱗のワンダーが詰まっています。
最近はやりと言ってもよい「死後」を見越した「終活」に秘められた不毛とは。ちまたで語られる「親ガチャ」とは、実は仏教の教えそのものだった?今、誰もが口にする「プラス思考」に隠される落とし穴とは何か。さらには、ものや人を所有物と見なす市場至上主義が持つ危険な本質。現代社会には、矛盾に満ちた考えが当たり前のこととしてまかり通っています。
直哉さんの語りは、人類の繁栄が人の幻想から形作られた、と語る歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏を思い起こさせるワンダーな一面を持っています。ぜひ、皆さんもワンダーを秘めた直哉さんの語りに引き込まれてください。今日とは異なる明日が見えてくるかもしれません。
このところ激しい寒暖差が続きます。くれぐれもご自愛ください。
それでは皆さんお元気で、またお会いします。

にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。