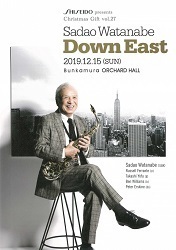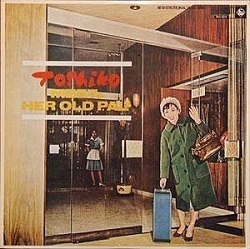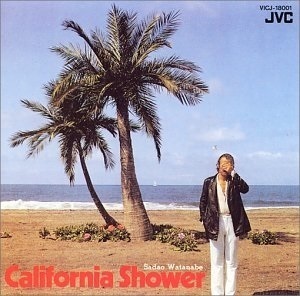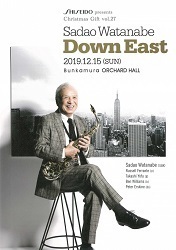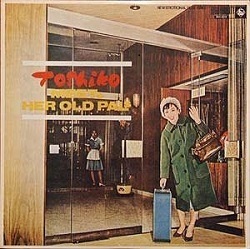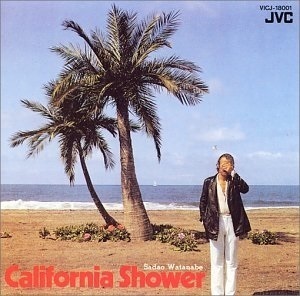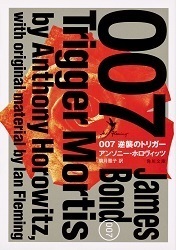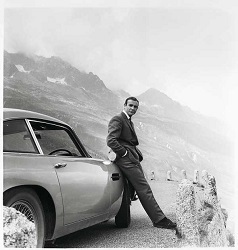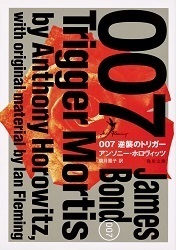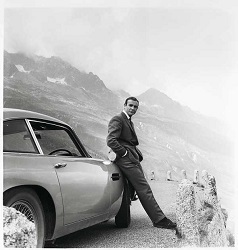こんばんは。
コートールド美術館展、第二章の最後を飾るのは、この美術館展のアイコンと言ってもよい「フォリー=ベルジェールのバー」です。
コートールド美術館は、美術研究を主務とするコートールド美術研究所に付随する美術館です。今回の美術展では、こうした美術館の特性を生かして、展示されている名画の特徴や芸術的な進取性などを解説しているところが大きな特徴となっています。
マネ晩年の名作であるこの絵にも様々な解説がなされています。
(マネ「フォリー=ベルジェールのバー」)
マネはこの絵を再作するにあたって自らのアトリエに、当時大人気であったパリのミュージックホール「フォリー=ベルジェール」のバーを創り、そこに実際のバーメイドを連れてきてモデルとしたと言います。このバーメイドの後ろは前面鏡張りとなっており、その鏡には観客席が写っています。このバーメイドの物憂げな表情も魅惑的ですが、その後ろ姿は鏡に映っており、さらに鏡に映る紳士を見ると、メイドはこの紳士と会話していることが分かります。
つまり、この絵を見ている我々はこの紳士の視線と同様の場面を目にしていることになります。しかし、この鏡の中は幻想的な世界です。まず、この角度から見るとメイドの後ろ姿や紳士の姿は非常に不自然な角度となっており、マネが故意に鏡の角度をゆがめていることが見て取れます。さらには、メイドの姿に焦点を合わせるために鏡に映る観客席の群衆はぼやかされていて、マネはそうすることで、この絵の効果を引き出そうとしていることがよくわかります。
実際の絵は圧倒的な迫力を持って我々の心に当時のパリを映し出しますが、晩年のマネは尽きることなく新しい文化と新しい技法に挑戦していたのだと改めて感動します。
【印象派の奥深さを知る】
数々の絵から得る感動で心を満たされながら美術展はいよいよ最終章へと向かっていきます。最後を飾る第三章は、「素材、技法から読み解く」と題されています。
この章では、19世紀に発明されたチュ-ブ入りの絵の具やカメラの発明と普及などの技術革新を画家たちが自らの作画にどのように取り入れようとしたか、その痕跡に焦点を当てていくことになります。さらにこの章では、印象派の次の世代へと進んでいくとともに、タヒチに渡った画家ゴーガンの絵を見ることができます。
まず目に飛び込んできたのは、くすんだ茶色の風景の中にぼんやりと描かれた馬上の主従の姿です。タイトルは、「ドンキホーテとサンチョ・パンサ」。作家はオノレ・ドーミネ。ドンキホーテは、御姫様であるドルシネアを守る騎士として、幻想の中の怪物に挑んでいく奇態な男ですが、凛々しく描かれたドンキホーテは、表情こそ描かれていないものの理想に向かう姿が象徴的に描かれていました。
この絵も未完の作品でしたが、ここからしばらく絵画展は未完の作品を紹介していきます。
ドガの未完作品は、窓辺の椅子に座る真っ暗な女性が描かれた「窓辺の女」、そして傘をさしてうつむく女性をななめ上の視点から描いた「傘をさす女」です。前作は、新しい絵の具を自ら調合して描こうとした作品でただ暗い印象ですが、傘をさす女は、貴婦人が傘をさしてうつむいている姿が習作的に描かれていて、ドガのセンスが光っている作品です。
未完の作品の中では、セザンヌの作品に目を奪われました。
(セザンヌ「曲がり道(未完)」)
「曲がり道」と題された絵は、72cm×92cmの大きなキャンバスに尖塔のある田舎の遠景が描かれています。この作品が感動を生むのは、描かれたすべての事物の輪郭がぼやけていることです。さらに色使いも田畑や森や草原と思われる風景の緑や青と画面の上部半分以上を占める空の淡い青で満たされており、尖塔である教会へと続く道が白と黄土色であがかれています。それは、まるで心の中の色をカンヴァスに映し出したようで、その淡さに心が洗われるような気がします。ピカソなどキュビズムの画家たちがセザンヌに影響を受けたと言われる所以が分かるような気がしました。
そして、次に現れるのはポスト印象派の代表ともいえる点描画の世界です。
点描画と言えば、スーラの「グランド・ジャット島の日曜日」が思い出されますが、コートールド氏が手に入れたのは、「クールブヴォアの橋」と題された作品です。この絵は、スーラが点描手法を全画面に用いた初めての作品と言われているそうです。この作品には豊かな水をたたえるセーヌ川河畔の風景が点描によって淡く描かれているのですが、その景色があの名画、グランド・ジャット島からの眺めだと知ると一層の感慨がわいてきます。
(スーラ「クールブヴォアの橋」)
この作品に続いて、小さなカンヴァスに描かれた点描画以前のスーラの作品が展示されています。「釣り人」、「船を塗装する男」、「水に入る馬」は、前作と同様にセーヌ川の河畔で描かれた作品と思われますが、画法はまさに印象派の油絵そのものであり、点描画以前のスーラのタッチを知ることができ、興味深い展示でした。スーラでは、小さいながらもさらなる点描画の意欲的な作品「グラブリームの夜明け」と題された美しい作品を見ることができました。
【ゴーガン その絵画の魅力】
スーラの次に現れたのは、ポスト印象派を代表するポール・ゴーガンの作品でした。
最初に展示されているのは、なんと絵画ではなく彫刻です。真っ白い大理石でできた彫刻は人の頭像です。凛とした若く魅惑的な表情の頭像は、なんとゴーガンの妻、メット=ソフィー・ガッドの姿を映したものでした。この作品は、ゴーガンが30歳ころの作品で、このころ彼は株式仲介人の仕事をしており、その傍らで芸術作品を作っていたと言います。その作品は、とても丁寧で美しく造形されており、ゴーガンの志がほの見える作品でした。
ゴーガンの最初の作品は、ゴッホとのアルルでの生活と決別したゴーガンがフランスのブルターニュ地方を描いた「干し草」です。この作品は、一面黄色で塗られた干し草を積む多くの人々がえがかれていますが、そこにはゴッホに似たタッチが感じられ、まだ印象派の影響が強いゴーガンの筆致を見ることができます。
ゴーガンといえば、南太平洋のタヒチ島で描かれた絵画が思い出されます。次の作品は、130cmのおおきなカンヴァスに描かれたタヒチ島の「テ・レリオア」です。この絵に描かれているのは、部屋の中に座る二人の女性とその横に猫。画面の左下には、幼い子供がうつぶせに眠っています。女性の奥にはタヒチ等の風景が描かれていますが、それが窓からの風景なのか画中画なのかは判然としません。
(ゴーガン「テ・レリオア」)
この絵の題名は、タヒチ語で「夢」をあらわしているそうです。描かれている女性二人も猫も全く別の方向を向いており、左右に掛けられたタペストリーに描かれる絵も民族的であり、その非現実性は題名そのものともいえます。ここの絵にはゴーガンが紡ぎ出した個性が前面に表出しており、心を動かされるのです。
そして、その画の衝撃は、次の絵に引き継がれていきます。その画は「ネヴァーモア」。
縦60cm×横116cm。横に長いカンヴァスには、横たわる全裸の女性が描かれます。ベッドに横たわる若い女性は左半身を下にして左手を頬に当てて両足をそろえて横たわっています。その表情は、タヒチ島の住民であり、何かを思案しているようです。ベッドの後ろには部屋の外で話をしている二人の女性の後ろ姿。さらに左の窓枠には、カラスのようなぶきみな鳥がとまっているのです。そのアンバランスな世界は、この世の不安を独自の映像と筆致で表現しており、その題名とも相まって妙に心をざわつかせます。
(ゴーガン「ネヴァーモア」)
この絵を見ると、ここにゴーガンの個性が極まっていると思いが強く感じられ、心が揺さぶられるような感動が沸き起こりました。
【印象派に続く作家たち】
ゴーガンの筆致に魅入られたまま歩を進めると目に入ってくるのは、ボナールの絵画です。
ボナールの作品は、フランスのヴェルノンに購入した家とそこから見た景色を描いた「青いバルコニー」、椅子に座る恋人の姿を描いた「室内の若い女」、課題のとおりの題名の「オリーヴの記と教会のある風景」の3点が続いて展示されています。中でも「青いバルコニー」に描かれた緑の木々の美しさは、ボナールの筆遣いをよく表わして心に残る作品でした。
ボナールに続いて展示されるのは、スーティンの「白いブラウスを着た若い女」。そして、その先に待っていたのは、一目でその作家とわかる「裸婦」でした。
(モディリアーニ「裸婦」)
その作家はモディリアーニ。モディリアーニと言えば、個性的な輪郭を持つ女性の肖像画がすぐに頭に浮かびますが、ここで展示されていたのは、一糸まとわぬ女性の半身像です。このときに描かれた5点の裸婦のうち2点はショウウィンドウに飾られたと言いますが、1917年当時、この絵は公序良俗に反するとして、警察から撤去を求められたそうです。なるほど、それほどこの作品が女性の裸体の魅力を的確に表現していたということか、と納得しました。この絵は、顔と体でまったく筆遣いが異なることが分かっており、モディリアーニの絵画の秘密の一端が込められた絵だということがよくわかります。
この章では、こうしたポスト印象派の絵画に囲まれるようにして、展示室の中心に多くのブロンズ像が展示されていました。なんといっても感動するのは、ロダンの作品たちです。
ロダンの作品は「静」と「動」をみごとに創り分けていますが、ここに展示された5作品を見るとそのどちらもが素晴らしい作品です。「叫び」と言う作品は、青年が不安そうな表情で大きく叫ぶ顔が描かれた造形ですが、そこにはリアルを超えた真実が表現されています。さらに「ムーヴマン」呼ばれるダンスを造形した3作品の躍動感は人間が瞬発する瞬間を切り取った造形美にあふれる作品です。ヨーロッパで活躍したという日本の女優「花子」を描いた作品は、不可思議な表情が魅力的な「静」の作品です。
そして、ブロンズ像の最後には、ドガの作品が展示されています。ドガは、たくさんの踊り子を描いた作品で有名ですが、このブロンズ像も踊り子を描いた作品です。この作品の踊り子は、とても変わった姿勢を取っています。その題名は、「右の足裏を見る踊り子」。題名の通り、右足を背中の方に持ち上げて、振り返って自分の右の足の裏を見ている踊り子。このポーズを描くのにドガ゙は10年以上の歳月を費やしたといいますが、やはり人の造形は美しいと改めて感じられる作品でした。
(ドガ「右の足裏を見る踊り子」)
こうして、すっかり魅入られる作品に出会うことができた美術展は終了しました。
今回のコートールド美術館展は、はじめてみる名画が次々に現れて、感動の連続に心が震えた美術展でした。あまりにも多くの名画に出会ったので展示室から出たあとにはしばし放心状態となっていました。この素晴らしい美術展を企画した多くの皆さんに心から感謝します。ロンドンには大英博物館やターナー美術館が有名ですが、これほど豊かな美術館があったとは、うれしい驚きです。
この美術展は、上野での展示を終了し、これから愛知、神戸で展示が行われます。名古屋、関西の皆さん。ぜひコートールド美術館展に足を運んでください。芳醇な芸術の世界にひたれること間違いなしです。
それでは皆さんお元気で、またお会いします。
〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。
にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。