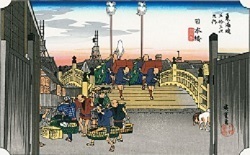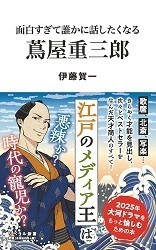こんばんは。
皆さんは、タイムスリップするとすれば、どの時代に行きたいと思いますか。
いくとするなら江戸時代です。江戸時代は言葉も通じるでしょうし、江戸は17世紀には世界で最も人口が多く、文化的にも栄えた都市だと言われています。さらに、江戸時代には交通も経済も発達しており、江戸、大坂、京都の3大都市を擁する日本は、当時の世界では先進国だったのではないでしょうか。
しかし、江戸時代は265年も続いた時代です。一世代を30年と考えるとすれば、8代にもまたがるわけですから、その間のどの世代に降り立つかによって境遇はずいぶん違うのではないかと想像します。一方で、世界的に見ても、人類史上これだけ長い間平和が続いた政権はまれなのではないでしょうか。そう考えれば、江戸時代の何処にに降り立ってもすぐに殺されることはなさそうです。
(江戸時代 交通網の起点 広重の日本橋)
時代の幸せ感から考えると、江戸時代は戦後の日本とよく似て平穏で平和な気がします。
確かに265年と戦後の80年が同じというのもおかしな話ではありますが、現代の進化速度を考えれば、当時の265年を80年と比較することは必ずしも不合理とは思えません。
徳川家康が征夷大将軍となり、江戸幕府を開いたのは1603年です。戦国時代から群雄割拠によって日本全国で戦いが続き、その結果、天下を統一した豊臣秀吉は、せっかく実現した平和にもかかわらず、あろうことか朝鮮に出兵し日本全国を疲弊させました。徳川家康が、大河ドラマのように「平和」を希求して天下を収めたとは思えませんが、家康が日本の繁栄を目指したことは間違いなさそうです。
戦後80年を江戸時代の年月に換算すると、現代の1年間は江戸時代の3年3ヶ月と考えることが出来ます。戦後の復興期は約10年。昭和30年代には高度成長期に入り、「もはや戦後ではない」と言われました。東京オリンピックの開催は昭和36年でした。その後、高度成長期は続き、その15年後には、バブル景気を招くことになります。
昭和の高度成長は、江戸時代、第5代将軍徳川綱吉の時代に好景気に沸いた元禄時代になぞらえられます。元禄が始まったのは、1688年。ここから1704年まで続きますが、この間に元禄文化が花開きます。読み物では、「好色一代男」の井原西鶴、俳句では「奥の細道」の松尾芭蕉、浄瑠璃で一世を風靡した近松門左衛門などキラ星のような才能が輝きます。
江戸幕府から元禄文化までは約100年。終戦から戦後復興を経てバブル景気まで約40年。江戸時代と現代は、よく似ていると思えてなりません。元禄時代には、様々な事件も起きています。元禄期には、かの有名な「赤穂浪士事件」が起きています。また、江戸も現代と同様に様々な災害に見舞われています。1682年には、八百屋お七で知られる天和の大火で大きな被害を受け、1703年には、元禄地震、元号が変った翌年には、浅間山の大噴火。さらに2年後には富士山の噴火、そして宝永地震と立て続けに災害に見舞われているのです。
これは、バブル崩壊、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、東日本大震災と大きな災害に見舞われた現在と重なるように思えます。
現代の日本は、幸いなことに「平和」が続いていますが、江戸時代と同様にこの平和が永く続くことを願います。
さて、江戸時代と言えば今年の大河ドラマでは、江戸の出版文化の新たなページを切り開いた粋な男、蔦屋重三郎が主役。あまり我々にはなじみのない名前ですが、なぜ彼が大河ドラマの主役となるのか、それを知るために一冊の本を読みました。
「面白すぎて誰かに話したくなる 蔦屋重三郎」
(伊藤賀一著 リベラル新書 2024年)
(伊藤賀一著 新書「蔦重」amazon.co.jp)
【蔦屋重三郎とは何者なのか】
蔦屋重三郎は、1750年に江戸の吉原で生まれました。バブルになぞらえられる元禄時代から下ること約50年、江戸幕府から公認されていた花街である吉原。そこで生まれ、そこで育った重三郎はいったい何をした男なのでしょう。
皆さんは、フランスで花開いた印象派の絵画はお好きですか。印象派と言えば、モネの睡蓮、ルノワールの少女、ドガの踊り子、それに続くゴッホ、セザンヌ、ゴーギャンなどなど、日本人には大人気の絵画群が思い起こされます。
こうした印象派の画家たちが大きな影響を受けたのが日本の浮世絵です。
葛飾北斎、喜多川歌麿、東洲斎写楽などなど、モネのジュベルニーのある自宅の食堂は浮世絵で満たされていました。また、ゴッホは、自らの絵画に生かすために多くの浮世絵を模写していました。また、ルノワールもジャポニズムを背景とした少女の絵を残しています。そして、皆さんもこうした浮世絵師たちの名前はよくご存じだと思います。
実は、世界に冠たる浮世絵師たちを世に出したプロデューサーが蔦屋重三郎だったのです。彼は、閉鎖的な江戸の出版文化に風穴を開け、江戸に新たな文化を根付かせることに成功しました。それは、アカデミックなものではなく、自らが江戸の大衆に受けると信じた黄表紙本や浮世絵、はたまた狂歌本を次から次へと世に出して、メディア王と言ってもよい活躍をしたのです。
驚きなのは、彼の生涯が47年に過ぎなかったという事実です。
江戸時代には、乳児の死亡率が高く、平均寿命は40歳前後と言われていますが、まさに「人生50年」を地で行ったといえるかもしれません。それにしても、70歳まで現役で働いている現代人から見れば短かすぎる人生ですが、彼の死に際は、その生き方同様に見事です。
江戸っ子と言えば、野暮を嫌い「粋」でけんかっ早く、人情に厚いとの印象ですが、蔦屋重三郎(以下、蔦重と言います。)も江戸っ子そのものだったようです。その経歴を見ると、蔦重は何事にもめげずにひたすら前進する、「前向き」の塊のように見えますが、実はその出自には悲しさが伴っています。
吉原で生まれた蔦重は、幼くして両親が離別するという悲しみを味わったうえ、その両親がどちらも引き取りを拒否したことから7歳にして、吉原の引手茶屋である喜多川家に養子として引き取られることになります。そして、吉原の引手茶屋の仕事を手伝いながら、義兄が開いていた引手茶屋「蔦屋」の軒先を間借りして、小さな書店を開きます。このとき蔦重は22歳でした。
【江戸文化を変えるまでの成長】
蔦重がなぜ書店を営もうと思ったのかは、想像するしかありません。
江戸の吉原と言えば、頂点に立つ花魁から、鼓楼の中に顔見せする数百人の遊女たちがその美しさを競いあう花街です。当時、この花街の遊女を紹介するガイドブックが販売されていました。その本は、俗に「吉原細見」と呼ばれます。この本の版元は日本橋の地本問屋「鶴鱗堂」で、ほぼ独占状態でした。蔦重は、吉原に培った人脈の力で、この本の販売代理店になることに成功したのです。つまり、「吉原細見」を仕入れて販売する商売を始めたわけです。
(歌麿が描いた吉原花魁の浮世絵)
ところが、小売りを初めて2年後、版元の「鶴鱗堂」の手代が上方の版元と同じ本を重版するという罪を犯し、「鶴鱗堂」では一時期「吉原細見」を出版することが出来なくなったのです。これをチャンスととらえたのが蔦重でした。
蔦重は、自ら吉原の内外に築いた人脈をフルに利用して、「吉原細見」に変る新たな吉原のガイド本を出版したのです。それは、吉原にある遊郭各店にいる花魁を花に見立てて紹介する遊女紹介本「一目千本」というガイド本でした。蔦重は、従来の単なる紹介本から花魁の絵図をふんだんに使って視覚に訴える小冊子を自ら出版したのです。
彼が巧妙だったのは、このガイドブックを有料で販売せず、吉原で最も裕福な客のみを相手する花魁にもたせて、無料で客たちに配布したのです。この本は、富裕層の顧客(上級武士や豪商)たちの間で評判となり、蔦重の本も順調に販売数を伸ばしたのです。
こうして順調に売り上げを伸ばした蔦重は、10年後には従来の「吉原細見」の版権を次々に買い取って、吉原ガイド本をすべて独占するまでに大きくなったのです。蔦重が統一して出版した「吉原細見」には、当時マルチな才能で人気者だった平賀源内が序文を書いたことから、大いに評判をとることになりました。
いま、大河ドラマではこのあたりが進行していますね。
「吉原細見」の独占までにも蔦重は、「貸本行」の株を手に入れ、さらに売り上げを伸ばし、義兄の軒先から独立し、「耕書堂」という店舗を立ち上げます。そして、寺子屋の教科書の出版、当時の小説の新ジャンルである黄表紙の出版にも手を広げます。
当時の江戸には、参勤交代で江戸つめとなっていた全国各藩の武士たちが集まり、さらには商家の次男、三男など、様々な人材が才能を発揮し、小説本を執筆していました。蔦重は、人脈作りに精を出し、信用と信頼を勝ち取り、老舗で黄表紙を書いていた恋川春町などの著者を引き抜きます。武家であった山東京伝も蔦重で黄表紙を執筆して大当たりします。
ここから勢いを増す蔦重は、当時、流行していた狂歌に目をつけます。狂歌とは、上の句、下の句で世の中を粋にニヤリとさせる短歌のことです。川柳は俳句と同じ五七五ですが、その短歌版が狂歌というわけです。狂歌の流行はすさまじく、蔦重は自ら号を持って狂歌の集まりである「連」を主催して、それを扱う狂歌本を出版。大いに売り上げを伸ばします。
蔦重は、こうした躍進を背景に、吉原から出て大手版元が集まる日本橋に出店することになるのです。
(葛飾北斎が描いた蔦重の「耕書堂」)
【試練をも糧にして進む蔦重】
昔から、「好事魔多し」と言いますが、順調すぎるときには割ることが起きるものです。
蔦重37歳のとき、江戸幕府では第11代将軍に徳川家斉が就きました。そして、その老中首座に松平定信が就任したのです。松平定信は、「寛政の改革」に着手し、倹約令を発布、世相の風紀引き締めを徹底したのです。
当時は流行していた黄表紙や狂歌絵本は、世の中を面白おかしく風刺することで人気を得ていました。幕府への批判と受け取られるような内容はすべて取り締まりの対象となり、蔦重の「耕書堂」も著者共々、お上から咎めを受けることとなるのです。
しかし、蔦重の超ポジティブな人生は、そんなことではめげることがありませんでした。幕府から資産没収の憂き目に遭った後、蔦重は喜多川歌麿、東洲斎写楽などの浮世絵の大流行の火付け役となるのです。
と、すべてのネタをばらすのは、「粋」ではありません。蔦重の人生の面白さは、ぜひ皆さんそれぞれで味わってください。その生き方を見れば、つまらない日常も楽しい人生に見えてくるかもしれません。
桜も散って、季節は夏へと向かいますが、まだまだ寒暖差は激しそうです。どうぞご自愛ください。
それでは皆さんお元気で、またお会いします。
〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。
にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。