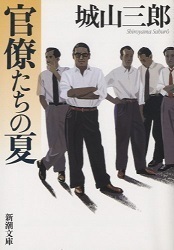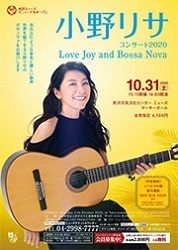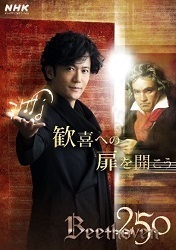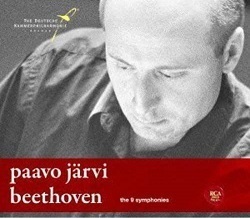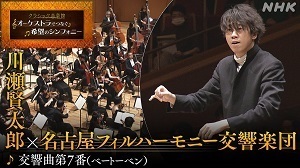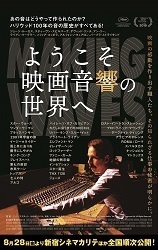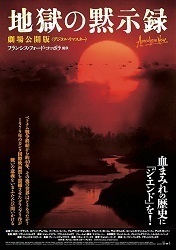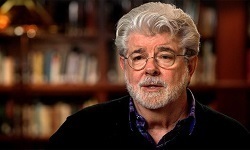<PR>
こんばんは。
平和と調和、そして多様性の祭典である北京オリンピックが閉会し、第2幕である北京パラリンピックの開会式が待たれる間隙の合間を縫って、ロシア軍が隣国ウクライナに侵攻し、事実上の戦争を仕掛けました。今もウクライナでは罪なき市民がロシアの攻撃によって殺戮され、死の恐怖に直面しています。
(ミサイル攻撃を受けたハリコフの住宅 jiji.com)
我々人類は、ここまで4000年の歴史の中で常に闘いに明け暮れていました。しかし、産業革命以降、我々は大いなる技術力を身に着け、一度に大量の命を奪うことができる兵器を手にしてしまいました。銃弾による殺戮、戦車や装甲車による衣食住や命の殲滅、航空機による空からの爆撃、海上では戦艦や空母による地上への砲撃、さらにはミサイルやICBMによる遠距離殺戮。
20世紀の戦争は、まさにそうした大量殺りく兵器によって世界が分断され、ある統計資料によれば、第一次大戦で亡くなった人は約852万人、第二次世界大戦では約912万人もの人々が戦争によって命を落としたといいます。
一口に912万人と言えば、それは単なる数値に聞こえますが、そこには亡くなった一人一人の人生、物語があります。我々は、コロナや災害で亡くなった方々には父親や母親、愛する娘や息子、そしていとおしい孫がいることを知っています。そして、人が生きている限り、そこに関わるたくさんの友人たちが取り巻いてくれているのです。
人はいくら生きても200年は生きられません。命は必ず尽きますが、命が続く間、我々は大勢の人々とかかわりながらなすべきことをなし、最後の瞬間まで命を燃やします。ところが、戦争は自らの意志、もっと言えば自然から授かっている寿命と関係なく、人の命を奪っていくのです。それは、そこに関わるすべての人の幸福を奪い、悲しみと苦しみのどん底へと叩き落す残酷な行為に他なりません。
理不尽な殺戮で大量の幸福を奪い、大量の不幸と絶望を生み出す人類の冒す最大の罪、それが戦争なのです。
【20世紀 我々は何を学んだのか】
第二次世界大戦で生み出された最終兵器は核兵器です。
科学は、この宇宙が創りだした物質の謎を次々に解き明かし、ついに原子をつなぎとめている途方もないパワーを引き出す技を手に入れました。実際に核爆弾は第二次大戦で我々の国、日本に投下され、広島では一瞬にして9万人以上の命が一瞬にして消え去りました。さらに、原爆の放射能により、その後、56万人もの人々が放射線に苦しんだとも言われています。さらに長崎にも原爆が投下され、7万人もの人々が亡くなりました。そして、被爆した方々は16万人以上に及んでいます。
核兵器は、一つの都市を地上から消し去るだけではなく、放射能により世界を不毛の大地と化してしまう恐ろしい兵器です。現在、核兵器を保有する国はアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、インド、パキスタン、そして北朝鮮であり、その数は13,000発と言われており、その90%をアメリカとロシアが保有しています。この数は、地球上の人類を35回以上殺戮できる数だとの計算もあります。
かつて、アメリカとソ連の冷戦下では、ソ連がキューバに核を持ち込むとの事件が持ち上がり、当時のケネディ大統領は核の使用さえも覚悟し、あわや核戦争にいたる一歩手前まで、事態は進みました。しかし、ソ連のフルシチョフ第一書記が最後の最後にキューバへのミサイル配備を取りやめるという理性ある判断に至たり核戦争は回避されました。
このときにアメリカ大統領とソ連書記長の間に直通のホットラインが敷かれたのは有名な話です。
(キューバ危機後のフルシチョフケネディ会談)
こうして核兵器は世界大戦の抑止力となりました。
しかし、核兵器が抑止力となった後も、世界では地域紛争が絶えることはありません。
1991年にゴルバチョフソ連大統領が辞任し、ソビエト連邦は崩壊しました。ソ連に変わりロシアが復活しましたが、それは共産主義ではなく共和国でした。アメリカとソ連の2極化した世界で繰り広げられた冷戦は終焉を迎え、世界にはアメリカ主導の平和が訪れると期待した人もいます。
アメリカは、冷戦終了後も戦争と紛争に明け暮れていました。
クウェートに侵攻したフセイン大統領の野望をくだくべく国連公認のもと連合軍を率いて行った湾岸戦争。21世紀に入ってからは、アルカイダによって仕掛けられた同時多発テロへの報復として、アフガニスタンへと攻め入り、タリバン政権を崩壊させ、民主政権を樹立させました。それに続いて、イラクのフセイン大統領が大量破壊兵器を隠し持っている証拠があるとの理由で、イラクに攻め入るや嵐のような空爆でフセイン大統領を逮捕し、死刑に処したのです。
21世紀のアメリカの戦争は、まさに「報復」ですが、アフガニスタンでは民主政権がイスラム国やタリバンの反抗、反撃に耐えられず、長くアメリカ軍が駐留し政権を支えてきました。しかし、昨年、バイデン政権がアメリカ軍を撤退するや否や、アッという間にアルカイダが各都市を占領。結局、アフガニスタンではアルカイダの政権が返り咲いたのです。
さらに、イラク戦争では、攻め入って勝利を得たアメリカ連合軍ですが、実はイラクに大量破壊兵器は存在していなかったというお粗末な結果が公表されました。
アメリカだけではなく、新たな共和国を立ち上げたロシアもアメリカに負けず劣らず紛争に明け暮れています。
崩壊後のソ連では、ロシア共和国を巡って権力の座に就いたエリツイン大統領は、自らの健康不安のために、後継者にプーチン氏を指名し、2000年5月にプーチン大統領が誕生しました。皮肉なことに後継者を指名した理由が、プーチン氏が民族主義者であると同時にエリツイン大統領の言うことに素直に従いそうだ、というものでした。しかし、元KGBのプーチン大統領は、まれにみる切れものだったのです。
(大統領就任式のプーチン氏 wikipediaより)
プーチン大統領は「強いロシアの復活」をかかげ、まず、国内で独立のために兵を挙げたチェチェン紛争に対し、徹底的な戦闘による力での解決で臨みました。チェチェンでは、多くの市民がこの内戦に巻き込まれ亡くなりましたが、ロシア政府軍は強大な軍事力でチェチェン独立派に『打ち勝ち、チェチェン紛争を抑え込んだのです。
さらに、エネルギー政策により経済力を回復させたプーチン大統領は、反民主主義へと大きく舵を切り始めます。アサド政権が強権を発動するシリアでは、イスラミックステイツや反政府軍の攻勢などが複雑に絡み合い、欧米が反政府軍を支援しましたが、プーチン大統領はアサド政権の政府軍を支援し、シリアでの空爆を遂行しました。
はたして我々人類は、二つの世界大戦を経験した20世紀の間に何を学んできたのでしょうか。
【侵略戦争はあってはならない暴挙】
今回のウクライナ侵攻の下地は、2014年にロシアがクリミア半島を併合しようとしたことがことの始まりのように見えます。
クリミア半島は、ロシア帝国の時代からロシアの貴重な不凍港のひとつとして、重要な戦略的役割を果たしてきました。しかし、ロシア帝国とオスマントルコ帝国の争いでクリミア戦争が起こり、その帰属はめまぐるしく変わり、さらには第一次世界大戦、そしてロシア革命を経て旧ソ連共和国の自治区の一つとしてウクライナの一部となりました。ところが、ソ連が崩壊したのち、2004年の選挙で親ロシア政権の大統領が当選しましたが、ウクライナ国民はその選挙に不正があったとして、再選挙を求めました。この運動はオレンジ革命とも呼ばれますが、再選挙によってロシアに距離を置く政権が発足しました。これ以降、ウクライナの大統領はあるときには西側の支援を受け、あるときには親ロシアの政策をかかげることを繰り返してきました。
(オレンジ革命時の首都キエフ wikipediaより)
クリミア半島はと言えば、歴史的に多くのロシア人が流入して居住していましたが、ソ連時代の1954年、ウクライナ出身のフルシチョフ書記長が主導し、当時のウクライナ・ソビエト社会主義共和国の州としてウクライナに帰属することとしたのです。これ以降、クリミア半島はウクライナ領とされてきましたが、そこに住むロシア人たちは、ソ連崩壊後、西側に揺れ動いていくウクライナの政権に反感を覚えていたことは想像に難くありません。
そして、2014年、クリミア州はクリミア自治共和国としてセヴァストプリ特別区とともに自らロシア連邦と一員となるとする条約に調印し、ロシアへの併合が行われました。
さらに今回、ロシアのプーチン大統領は軍事侵攻の前々日、ウクライナ国内のロシア人居住地であるドネツク州を「ドネツク人民共和国」、ルガンスク州を「ルガンスク人民共和国」として独立承認することを閣議決定し、独立を承認する大統領令に署名しました。
そして、2月24日、ウクライナがロシア人に対してジェノサイド(大量虐殺)を行っており、ロシア人の命を守るためにウクライナに侵攻する、と宣言しベラルーシ国境近くの北側とクリミア半島から、そして、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国からの軍事派遣要請に従って東側からウクライナ国内に侵攻を行ったのです。
(独立承認を発表するプーチン大統領 mainichi.com)
それは、ロシアの一方的な宣言によって行われ、首都キエフにはロシア軍が迫り、南部や東部の中核都市が一斉にロシア軍に侵略されるという事態に至りました。
ウクライナとロシアの間には歴史的にも近年にも領土をめぐる紛争があったことは事実ですが、ドネツクやルガンスクの東部では紛争停戦のため、2015年にミンスク合意が締結されました。にもかかわらず、ロシアはこれを無視して一方的にウクライナに攻め入ったのです。
ウクライナという国際的にもその主権が認められた国家に理由はともあれ、一方的に軍事浸入を行い、国家、国民を殺戮することは国際ルールを無視した一方的な宣戦布告に他なりません。これは、これまでの国際法に照らしても国際ルールをすべて無視する暴挙、国家侵略としか言いようがありません。
【一日も早く市民の殺戮をとめなくては】
ウクライナの市民は、突然蹂躙された国家がロシアに征服されないために高齢者や子供とその母親を除いてすべての国民がロシアと闘う決意を固めています。そして、欧米からの軍事支援も効果を挙げて、ウクライナはロシアのキエフ侵攻を強い抵抗によって食い止めている状況です。
恐らく侵攻後、数日でキエフを制圧し、ロシアの傀儡政権を打ち立てようともくろんだプーチン大統領の戦略は、ウクライナ国民の予想外の頑強な抵抗により侵攻後1カ月以上も遅れ、破たんしつつあります。このため、ロシアはロシア国内黒海に進出した戦艦から数百発ものミサイルを発射し、ウクライナの主要都市を空爆しています。その初期には、軍事施設を攻撃していたミサイル郡ですが、思わぬ抵抗へのイラダチと停戦をできる限り優位すすめるとの目的で、学校や病院、避難先である劇場など、市民が避難している施設への無残な攻撃を続けています。
(ミサイル攻撃を受けた避難先の劇場 news.yahooより)
ソ連崩壊後にロシア共和国の大統領に就任して以来22年間、プーチン大統領は極めて冷静で的確な政策を強力に推し進めることにより、ロシアをエネルギー大国に押し上げてその経済を立て直し、チェチェン独立に対しても強権を発動して軍事力で制圧して国内をまとめてきました。しかし、旧ソ連時代の衛星国が次々に革命のために民主主義政権へと移行し、その最後の砦がベラルーシであり、ジョージアやモルドヴァなども独立し、確かにウクライナはクリミアも含めてロシアにとっては死守すべき砦となったとき、プーチン大統領はその戦略を誤ったとしか思えません。
市民を狙い、無差別殺戮を行うプーチン大統領は、もはやかつてロシアを侵略したナポレオンやヒトラーと何ら変わらない犯罪人、殺戮者に成り下がりました。
心ある国際社会の国々とその市民は、あらゆる手段を使ってロシアの暴挙を止めることが必要です。東部の都市マリウポリでは、40万人の住民が避難もできず、電気、ガス、水道も止まり、食料さえもなくなっていると言います。あまつさえ、ロシアはマリウポリに降伏を申し入れ、さらなるミサイル攻撃を続けています。ウクライナ市民は降伏を拒否しましたが、この都市の市民を救うためにもプーチン大統領に不毛な戦争の停止を選択させる必要があります。
皆さん、ウクライナ市民のためにも、我々の未来のためにも、心を一つにしてこの戦争にNOを言い続けましょう。
それでは皆さんお元気で、またお会いします。
〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。
にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。