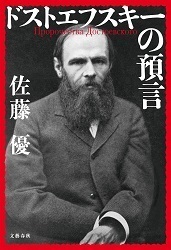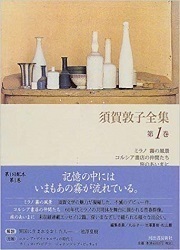こんばんは。
前回パリでオリンピックが開催されてから100年となる今年、華やかにパリオリンピックが開幕しました。
7月26日、セーヌ川を舞台として繰り広げられた開会式。スティッフパーソン病症候群という精神疾患に罹病し、闘病中であったセリーヌ・デュオンがエッフェル塔のステージに登場し、見事な歌唱で「愛の賛歌」を歌い上げたとき、その時間を共有できたことは思わず熱い想いがこみ上げてくる感動のひとときとなりました。
そして、始まったオリンピックは、日本代表の選手たちが躍動する感動の舞台となったのです。
男子代表団体戦での大逆転劇や東京オリンピックのリベンジを果たした男子ゴルフの松山英樹さんの我慢のゴルフ、男子バレーボールのイタリアとの壮絶なジュースの連続、スケートボード堀米選手の土壇場での大逆転。どれもこれも胸を振るわす感動を味わうこととなりました。
(男子団体逆転金! nikkei.comより)
結果、柔道、体操、フェンシング、スケートボード、そしてレスリングと、日本は20の金メダル、12の銀メダル、13の銅メダルを獲得し、平和の祭典において力を発揮しました。そのすべての選手に感動をもらいましたが、オリンピックが終わった今思うのは、様々な競技における栄枯盛衰に隠された、スタッフを含む人々が費やしてきた、想いと時間の尊さです。
今回のオリンピックでは、一時期、メダルの数が激減していた柔道が復活し、混合団体を含めて7つの金メダルを獲得。レスリングでも劣勢であった男子が、4つの金メダル、銀メダル1つを獲得しました。過去、涙をのんだ選手が多くいた種目で、これだけの成果を上げるのには、選手はもちろん、スタッフも並々ならぬ鍛錬と努力がどれほどのものだったのか、心が動きます。
今回のオリンピックでは、日本のお家芸だった競泳やアーティスティックスイミング、サーフィン、球技では、サッカー、バスケットボール、バレーボールでは、残念な結果に終わりました。
もちろん、すべての競技で日本代表は持てる力を発揮して白熱の接戦を展開してくれました。すべての競技は、世界に届かないときもあれば、世界一になるときも巡ってきます。世界に伍するためには、競技に携わるすべての人々がたゆまない分析と検証と努力を重ねることが必要なのです。
閉会式では、俳優のトム・クルーズさんが、スタジアムの頂点から映画のいちシーンのように舞い降りて、オリンピック旗を手にして、これまた映画のようにバイクに乗って走り去っていく姿にドギモを向かれました。次回のオリンピックはアメリカ、ロサンゼルスです。大谷翔平選手、八村塁選手でもよく知られる街で、日本選手が躍動する姿がいまから楽しみです。
そして、8月28日から行われるパリパラリンピックでの日本選手たちの晴れ姿もしっかり応援したいと思っています。
さて、オリンピック話が長くなりました。今回ご紹介するのは、60年以上前に上梓され、昨年、「岩波新書のカラー版として再版された名著です。
「カラー版 名画を見る眼Ⅰ―油彩画誕生からマネまで」
(高階秀爾著 2023年 岩波新書)
(「名画を見る眼Ⅰ」 amazon.co.jp)
【すっかり遠くなった美術館】
拙ブログに訪れていただいている皆さんの中には、美術館や美術展に関する記事がめっきり減少したとなげいている方もいらっしゃるかもしれません。実を言うと、コロナ禍で外出自粛となり、美術館に足を運ばなくなってから、今日まで一度も美術館に足を運んでいないのです。人間というのは惰性の動物で、一度行かなくなると映画も美術館もすっかり足が遠のいてしまします。
そうはいっても、昨年の四国旅行の時には徳島の大塚国際美術館を訪れたり、今年の6月には皇居内の三の丸尚蔵館で、国宝の若冲「動植綵絵」4幅、同じく国宝、狩野永徳「唐獅子図屏風」が公開されたので見に行きました。いずれも素晴らしい作品でした。
そんな中、いつものように本屋さんを巡っていると岩波新書の中に「名画を見る眼」との書名をみつけました。本を開いて奥付を見ると初刷が1969年となっていますが、重版となるカラー版では、各項目で紹介される絵画がカラーで掲載されており、その絵画もあまりに有名な作品ばかりです。美術館に行くと、心を動かされるような作品でも、その深い意味はなかなかを知ることはできず、作者と制作年代がわかる程度で、もっと作品の背景や作者の思いを知りたくなります。
それを思い出して中を読むと、まさに知りたいと考えていた名作の背景や考察がそこに記されています。思わず、本を持ってカウンターに走りました。
いったいどのような名画が紹介されているのか、まずは目次を見てみましょう。
Ⅰ ファン・アイク「アルノルフィニ夫妻の肖像」
――徹底した写実主義
Ⅱ ボッティチェルリ「春」 ――神話的幻想の装飾美
Ⅲ レオナルド「聖アンナと聖母子」 ――天上の微笑
Ⅳ ラファエルロ「小椅子の聖母」 ――完璧な構成
Ⅴ デューラー「メレンコリア・Ⅰ」 ――光と闇の世界
Ⅵ ベラスケス「宮廷の侍女たち」 ――筆触の魔術
Ⅶ レンブラント「フローラ」 ――明暗のなかの女神
Ⅷ プーサン「サビニの女たちの掠奪」
――ダイナミックな群像
Ⅸ フェルメール「絵画芸術」 ――象徴的室内空間
Ⅹ ワトー「シテール島の巡礼」 ――描かれた演劇世界
ⅩⅠ ゴヤ「裸体のマハ」 ――夢と現実の官能美
ⅩⅡ ドラクロワ「アルジェの女たち」 ――輝く色彩
ⅩⅢ ターナー「国会議事堂の火災」 ――火と水と空気
ⅩⅣ クールベ「画家のアトリエ」 ――社会のなかの芸術家
ⅩⅤ マネ「オランピア」 ――近代への序曲
あとがき
『カラー版 名画を見る眼Ⅰ』へのあとがき
【ヨーロッパ絵画の歴史と傑作】
美術館で絵画を鑑賞する動機には、彼女とのデートの場も含めて人それぞれですが、やはりアーティストが描いた「絵」の現物を見ることで、大きな感動を味わうことが出来る、ことが最も大きいのではないでしょうか。
昨年、四国の国際大塚美術館を訪れたときのことです。
この美術館は、世界中の名画を実物大の陶板で再現するという素晴らしいコンセプトの美術館で、建築上の制限から地下3階、地上2階の建物の5フロアに古代・中世から、ルネサンス・バロック、近代、現代とすべての時代の実物大の作品が展示されています。圧巻なのは、システィーナ礼拝堂そのものが再現されており、その壁面、天井がミケランジェロの天井画とあの「最後の審判」で彩られているフロアです。
(ミケランジェロ「最後の審判」 wikipediaより)
地下3階の古代から地上1階のバロックまでは、見るものすべてが迫力満点で、感動にあふれた展示でした。その陶板で創られた複製は、実物大で創られた、色合い、質感までを再現した見事な風合いを持つ作品で、全く遜色がないものと感じられたものです。
しかし、地上1階から地上2階にかけて展示されている印象派前後の作品を見たときに、妙な違和感を覚えるようになりました。拙ブログでもご紹介の通り、私はフェルメールとモネに眼がなく、フェルメールやモネの作品が来日したときには必ずと言っても良いほど美術展に足を運んで、実際に描かれた絵画に触れて感動を味わってきました。
この美術館で、フェルメールやモネの陶板を見たときには、実物を見たときのわき上がるような感動を味わうことが出来なかったのです。違和感の正体は、実際に描かれた絵画に込められたアーティストの情念を感じることが出来ないことだったのです。
やはり芸術作品は、音楽も含めてリアルに触れなければ大きな感動を得ることは出来ないようです。
そして、本物を見て感じる感動は、その絵画に対する予備知識があればより大きく感じることが出来るようになります。そうした意味では、こうした本を読んで、古今の名作に秘められた背景や物語を知った上で、「絵画」を鑑賞すればより大きな感動を味わうことが出来るのです。
この本では、名だたる名画と美術史に足跡を残した画家たちの歴史が、名画とともに鑑賞することが出来て、これまで見たことのある絵画であっても新たなワンダーを味わうことが出来るのです。特に、ルネッサンスが始まるイタリアで培われた古典主義からはじまり、貿易で栄えたオランダで生まれた写実主義、フランス王政の元で育ったバロック絵画、イギリス・パリで生まれ始めた近代絵画への胎動。この本では、その美術史の流れを余すことなく味わうことが出来ます。
【目から鱗が落ちる名調子】
この本の魅力は、それぞれの絵画や画家とその時代を語る独特の語り口にあります。
私が大好きなイギリスの画家、ウィリアム・ターナーで取り上げられているのは、19世紀の一大事件、イギリスの国会議事堂の大火災を描いた「国会議事堂の火災」です。この絵に描かれた火災の炎はまるでうねるように多様な色彩で、絵の中心にテームズ河にかかる橋とともに鮮やかに描かれています。
(ターナー「国会議事堂の火災」 wikipediaより)
この絵はとても有名で私も一度目にしていますが、知らなかったのは、ターナーはこの絵の他に二枚、国会議事堂の火災を描いているという事実です。この作品は、かなりの遠景で河の対岸からの視点で描かれています。しかし、他の2作品はもっと近くから描かれており、驚くことにそのうちの1枚は、まさに火災が起きている目前で燃えている建物を描写しているのです。さらには、そこには集まった野次馬たちまでがみごとに描かれているのです。
この時代、画家たちには外で絵を描くという習慣がありませんでした。もちろん、外で実物を前にスケッチを描き、後にアトリエでカンヴァスに書き上げるわけです。にもかかわらず、この絵でターナーは現場に水彩絵の具を持って行き、その場で色彩を入れたというのです。ターナーの色彩に対する思い入れはハンパではなかったのです。
また、当時の展覧会に自らの絵画を出品すると、会場に展示された自分の絵画に最後の最後まで手を入れていたというのです。この話は当時から有名だったそうで、ある展覧会では隣にコンスタブルの「ウォータールー橋の開通式」という絵が展示され、コンスタブルがその絵に最後まで手を入れていました。隣のターナーは、コンスタブルが入念に自らの絵を完成させた後、やってきてお隣の自らの絵に赤い印を書き入れました。
いったいなぜ?
その顛末はこの本でお楽しみください。著者は、ターナーは本質的には幻想作家であったかもしれない、と語っています。
この本では、どの絵画も、どの画家も、様々なエピソードで彩られています。それを読むと、ここで紹介された絵画をぜひこの目で味わってみたいとの気持ちがわき上がってきます。皆さんも、ぜひこの本で名画の歴史とエピソードを味わってください。あらためて、絵画鑑賞の魅力を感じること間違いなしです。
それでは皆さんお元気で、またお会いします。
〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。
にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。