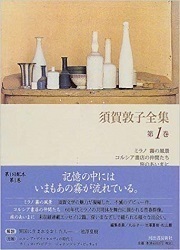こんばんは。
本屋さんで「須賀敦子」という文字を見ると、自然に反応してしまいます。
3年ほど前に文庫化された湯川豊氏の「須賀敦子を読む」を本屋さんでみつけたときにも、その場で手に入れてアッと言う間に読んでしまいました。湯川さんは生前の須賀さんと編集者として二人三脚で歩んでいた方で、須賀敦子文学の卓越した評論者であるだけではなく、心から須賀さんに寄り添った愛情あふれる著書を上梓したのでした。
この本を読むと、須賀さんの文学に対する意志は物心つくころからすでに形成されていて、自らを生きることに常に真剣であり、様々な変遷を経て生き抜く間にも常に「書く」ことを意識していたことが良く理解できます。須賀さんが60歳近くに自らの文章を練り上げて、読む人の心に限りない郷愁とはかなさを感じさせることができたのも、それまでの「書く」ことに対する鍛錬が実を結んだからに他ならないのだと思います。
語られるエピソードと語る言葉が一体となって、人の心に潜む様々な思いをいつも感じさせてくれるのです。
そんな中で先日本屋さんを巡っていると、またしても「須賀敦子」という言葉が目に飛び込んできました。すぐに購入したのは言うまでもありません。
「須賀敦子の旅路」(大竹昭子著 文春文庫 2018年)
この本は、2001年から2002年にかけて3冊に渡って上梓された単行本を底本としています。それは「須賀敦子のミラノ」、「須賀敦子のヴェネツィア」、「須賀敦子のローマ」と題された随筆です。須賀敦子さんは1998年3月に惜しまれつつ帰らぬ人となりましたが、その理知的でありながら心に染み入る美しい文章は、60歳でデビューするや文学界に衝撃をもたらしたと言います。
大竹さんも須賀敦子さんの文章に魅せられた一人で、須賀さんの生前から親交を深めたと言います。昨年は没後20年という節目の年となり、過去に上梓した文章に新たに「須賀敦子の東京」ともいえる「東京編」を加えて文庫本として上梓したものが本書となります。
(文庫「須賀敦子の旅路」 amazon.co.jp)
【旅路は原点 ミラノから】
須賀さんのデビュー作は「ミラノ 霧の風景」です。
このデビュー作には、須賀敦子さんの12のエッセイが重ねられています。相当に悩みつつ作品を選んだと思われますが、選ばれているのは長く暮らしたミラノから仕事や旅で訪れたイタリアの各都市でのエピソードや想いを書き綴っています。そこに記された都市は、ジェノワ、トリエステ、ヴェネツィア、ナポリ、ベルージャ、など多彩です。
この作品は、講談社エッセイ賞、女流文学賞を受賞していますが、上梓された当時には「ミラノ 霧の風景」のような随筆のあり方はなかったのではないかと思います。随筆と言えば、有名作家が日常を綴ったり、交遊録を記したり、趣味や食べ物の話をする文章を思い起こします。また、都市を訪れるのであれば、旅行記としてその地を紹介する文章を思い起こします。
須賀敦子さんのエッセイは、それ自体が文学作品であり、文章そのものが我々に様々な思いを語りかけてきて、我々の心を動かしていきます。例えば、デビュー作の題名となっている「霧」ですが、エッセイでは次のように記されています。それは、一片の詩のように響いてきます。
「乾燥した東京の冬には一年に一度あるかないかだけれど、ほんとうにまれに霧が出ることがある。夜、仕事を終えて外に出たときに、霧がかかっていると、あ、この匂いは知っている、と思う。十年以上暮らしたミラノの風物でなにがいちばんなつかしいかと聞かれたら、私は即座に「霧」とこたえるだろう。」
須賀敦子さんは、13年間暮らしたミラノでの生活の中で、日本文学をイタリア語に翻訳したり、イタリアの文学を日本語に翻訳することを仕事としていました。彼女はその中で、書き手が文章を書くと言う行為、想いを言葉にする方法、を客観的に見る術を身に着けたのだろうと想像します。なので、須賀さんの文章は、自分を外から見てその内側にある感情や感性を豊かに語る文章となっているのだと思います。
竹内昭子さんは、この「須賀敦子の旅路」をまずミラノの旅からはじめています。
なぜならば、「ミラノの霧」の言葉に込められているように、「ミラノ」を生きた須賀敦子さんこそが、その後の人生の原点であったと言っても過言ではないからなのです。竹内さんは、須賀敦子さんの透徹した文章はなぜその文章なのか。そのことを知るためにミラノ、ヴェネツィア、ローマを訪問し、そこで感じた須賀敦子さんを記憶と文章にとどめています。それは、結果として須賀敦子さんの文学の魅力を改めて解き明かす旅となりました。
例えば、「ミラノ 霧の風景」に収められたエッセイに「鉄道員の家」という1篇があります。
須賀敦子さんは、1958年29歳のときに2度目の留学先としてイタリアに渡ります。須賀さんはもともとキリスト教カトリックの考え方に強い想いをもっていましたが、ミラノの教会内にあるコルシア書店を知って、そこでの触れあい、議論、会話に魅入られます。そのテーマは宗教における思想と行動、との狭間にある何かでした。そして、そこで書店の運営に協力していたベッピーノォと知り合って1960年に結婚するのです。
(書店のあったサン・カルロ教会 4travel.jp)
結婚とは、ベッピーノォだけではなく、その家族と一緒になるということです。ベッピーノォの父親はミラノ・ローマ線の鉄道員であり、その住まいは鉄道員官舎だったのです。このエッセイは自分が嫁いだ実家の家を描いていました。竹内さんはミラノの旅で須賀さんの住んだアパート、毎日通っていたコルシカ書店、などゆかりの地を巡っていますが、このご両親の実家にも訪れています。
須賀さんが暮らしたころからは、すでに40年のときが過ぎていたのですが、その鉄道員宿舎は当時のとおりその場所に建っていたのです。そこから見える裏の原っぱも全く変わらず、あまつさえ、線路を切り替える装置のある鉄道小屋も当時のまま残っており、その係員が声をかけてくれて、わざわざ鉄道小屋の中にまで招き入れてくれます。
そうした中で、大竹さんは、須賀さんの両親の実家のベットの中で、寒い夜に線路のうえで汽車の車輪が軋む音が長い時間続き、その音で異文化の中にいる日本人である自分を感じていたとの文章を思い出して、その孤独に想いを馳せることになります。
【ヴェネツィア、そしてローマ】
ミラノは、須賀さんがイタリアでの13年間のほぼすべてを過ごした地でしたが、ヴェネツィアとローマは少し趣が異なる地となります。
1967年、結婚の6年後に須賀さんの夫ベッピーノォは病気によって急逝しました。そして、その傷をいやす暇もなく、母親の病気が悪化し日本に一時帰国。母親の病気は小康を得ましたが、祖母が亡くなり、さらに父親はがんに侵されます。ミラノにベッピーノォの家族を残してきた須賀さんは、その父親を日本に残してミラノへと戻ります。
イタリアの人たちは、ヴァカンスの時期になると誰もが休暇を取り避暑地へと出かけてしまいます。避暑に出かけないのは、家族がいないか、よほどお金のない貧乏人だけであり、ミラノはその時期には人っ子一人いなくなります。長く過ごしたミラノの友人たちは、傷心の須賀敦子さんに心を寄せて避暑に誘ってくれますが、彼女自身は同情を寄せられているような気がしてすべて断ってしまいます。
そんな中、昔からの友人であるドイツ人のインゲからヴェネツィアのリド島で部屋をシェアして過ごそうと誘われます。他の友人たちは自分をなぐさめようと誘ってくれるのに比べて、インゲは他の友人と割り勘で、とフラットに誘ってくれたので、須賀敦子さんは心を解いてヴェネツィアへと出かけるのです。著者の竹内さんは、須賀さんの後を追うように30年後にリド島を訪れます。
須賀さんがヴェネツィアを訪れた経緯は、亡くなった後に上梓された「地図のない道」に載った作品に記されています。その旅は、須賀さんが日本に帰国した後に大学で日本文学の研究のために再びヴェネツィアを訪れた旅へとつながっていきます。須賀さんが大好きだったと言うザッテレ河岸の描写はまるで竹内さんが須賀さんと想いを一つにして語り合っているように思えて、心が温かくなりました。
(須賀敦子さんが愛したザッテレ河岸 4travel.jp)
あらためて、「地図のない旅」を読みたいと心を新たにします。
さらにローマの旅は、1958年に須賀さんが29歳にて一度帰国した日本から再びイタリアへの留学へと踏み切った新たな人生がスタートを切ります。巻末に掲載されている須賀さんへのロングインタビューで、竹下さんの「カトリックに関してお話ししてください。」との質問に「その話はあまりに長い話になるので、ここではやめておきます。」と答えていますが、ローマには、キリスト教カトリックの総本山バチカン公国があり、その中心には聖ピエトロ教会の荘厳な建物がそびえています。
須賀さんが二度目の留学でローマの寄宿舎に入った年、聖ピエトロ教会では教皇ピウス12世が亡くなり、コンクラーヴェが行われました。新たな教皇には76歳のロンカッリ枢機卿が選ばれ、ヨハネ23世となりました。ヨハネ23世は約5年間教皇を務めて亡くなりましたが、その遺体は腐ることがなく、ヨハネ・パウロ2世によって祝福されました。大竹さんの旅は、ちょうどこのヨハネ23世の復活祭の日と重なっていました。
須賀さんのローマには、氏の人生にとって重大なテーマが埋められています。
カトリック教会の教皇ももちろんですが、須賀さんが文学の方法に導かれたイタリアの作家ナタリア・キンズブルグやローマの街角で偶然に出会った彫刻家ファッツィーニとその弟子の日本人Oさんとの邂逅。さらには、「ハドリアヌス帝の回想」を記したユルスナールを追った「ユルスナールの靴」にも通じています。第二の留学先をイタリアとした須賀さんにとって、ローマはカトリックと芸術、そして文学と深く交わった地だったのです。
大竹さんは、「私」として語られる「須賀敦子」の足跡を追ってローマを巡っていきます。
【須賀敦子さんの東京】
ミラノ、ヴァネツィア、ローマで「須賀敦子」の心を追った旅は、須賀敦子さんが亡くなったのちに、その人生と文学を改めて問い直すために行われたものでした。今回、3分冊で語られた旅が一冊の本にまとまられたわけですが、この文庫には新たな「須賀敦子」への旅が記されています。
それは、東京編です。
須賀さんは、1967年夫のベッピーノォ氏を突然の病気で失ってからも家族を支えてミラノに留まっていましたが、1971年意を決して日本に帰国しました。氏が最初の作品を上梓したのは1990年ですから、帰国からデビューまで20年近い歳月を日本で過ごしていたことになります。その作品は、まるで昨日までイタリアに住んでいたような新鮮で繊細な筆致で穏やかに記されています。いったいなぜ、作品を上梓するまでにそれだけの歳月が必要だったのか。
(須賀敦子全集 第1巻 amazon.co.jp)
竹内さんは、「ローマ編」の最後の「ノマッッドのように」で、イタリアから帰国してから自らの文学を創造するまでの間、須賀敦子の中でどのような葛藤があり、何が自らの作品の執筆のきっかけとなったのか。そのことに想いを致し、なんとか謎を解消しようと言葉を重ねています。しかし、それはひとつの仮説を述べたにすぎないのです。
それから18年の年月を経て、今、改めて東京において須賀敦子さんがどのような生を生きたのか。そのことに再び挑んだのです。
その旅は、これまで知ることのなかった日本での遍歴の中で城あった人々への取材と須賀さんの足跡を追いかけることで成し遂げられます。これまで知られていなかった人々との深い交流。その証言によって、須賀敦子さんの生きることにかけた想い、そして文学に託した思いが解き明かされていくのです。
その美しい文体を手に入れるまでの変遷、その文体で我々に届けたかった想いとは何か。須賀敦子さんが思い描いていた「文学」とはなにか。
皆さんもこの本で、その謎を解き明かす旅を味わってください。生きることの深みを知ることができるに違いありません。
それでは皆さんお元気で、またお会いします。
〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。
にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。