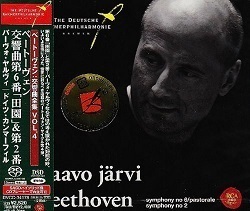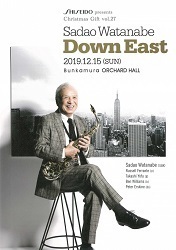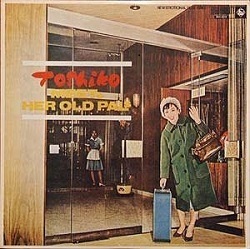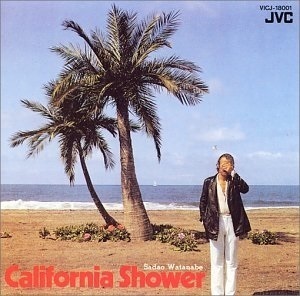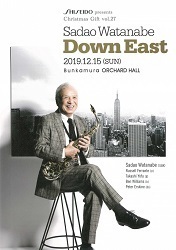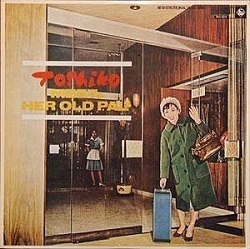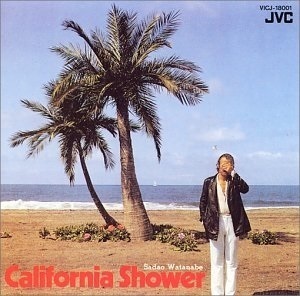こんばんは。
ビートルズと聞いただけで心が躍るのは、いったいなぜなのでしょう。
2023年11月2日、全世界に向けてビートルズの新曲が発表されました。その曲は、”Now And Then”。全世界のビートルズファンが心から待ち望んだ新曲は、我々に感動を運んでくれました。この曲は、全英ヒットチャートで1位を獲得。ビートルズの全英初1位の曲は、1963年の「フロム・ミー・トゥー・ユー」だったと言います。ビートルズは、60年を経て全英チャートで1位を獲得したはじめてのバンドとなったのです。
ビートルズが解散してから53年。この間にジョン・レノンは1980年に凶弾に倒れ、2001年にはジョージ・ハリスンが病没し、現在は81歳のポール・マッカートニーと83歳のリンゴ・スターがビートルズのメンバーです。新曲は、かつてジョン・レノンがピアノ弾き語りでカセットテープに残したデモからAIによってジョンの声のみを抽出し、そこに生前のジョージのリードギターを重ね、さらにはリンゴとポールがスタジオで実際に演奏して録音し完成させた、正真正銘のビートルズの作品です。
(最新シングル「Now And Then」amazon.co.jp)
しかし、ビートルズの音楽に心が動かされるのは、その革新性とその革新性を創造した4人のエネルギーに人々が感応するからなのです。
確かに新曲はそうした感動を思い起こさせてくれるアイテムではありますが、やはり彼らが残してくれた213曲の楽曲と13枚のアルバムほど我々の心を揺さぶるアイテムはありません。いったい、彼らはどのようにしてロックにあらゆる音楽の要素を融合させ、ビートルズ以外の何者にも作り出せない音楽を世に出したのでしょうか。
その秘密は、これまでデビュー当時から彼らの成長の糧であったプロヂューサーのジョージ・マーティンやレコーディングエンジニアのジェフ・エメリックなどがその著書によって解き明かしてきました。特に、ロックを芸術にまで高め、時代を変革したと言われる「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」がスタジオでどのように創造されたか、その4人が生み出した化学反応と進化を描き、心からの感動を呼び起こしてくれました。
ビートルズは、1966年8月にライブ活動を停止し、そこからスタジオでの音楽活動に専念しました。その最初のレコーディングセッションが「サージェント・ペパーズ・セッション」です。それは、「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」と「ペニー・レイン」からはじまり、アルバム最終「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」のオーケストラによるクレッシェンドまでの、天才たちのアイデアと実験に満ちたおもちゃ箱のようなスタジオワークだったのです。
ビートルズは、この後、唯一の失敗と言われる「マジカル・ミステリー・ツアー」を経て、グループとしての活動から一度距離を置き、メンバー個々の音楽性に重きを置いた2枚組のアルバム「ザ・ビートルズ」を発表します。このアルバムは、それまで父親のようだったプロデューサー、ジョージ・マーティンと距離を置き、それぞれが自由に音楽を創造する試みでした。この頃、彼らは理想の創造の場として設立した会社「アップル」が暗礁に乗り上げ、さらにデビュー当時から頼りにしていたマネージャー、ブライアン・エプスタインが亡くなり、その後継者問題も抱えていました。
そうした背景から空中分解しそうなビートルズでしたが、ポールは昔のビートルズに帰ることを夢見てある企画を提案します。それが、映画「レット・イット・ビー」へとつながる「ゲット・バック・セッション」でした。このドキュメントは、一昨年、映画のために撮りためてあった60時間にも及ぶセッション映像を新たに編集した「ザ・ビートルズ:Get Back」として公開されました。このセッションは、ビートルズ最後のライブ、アップル社屋屋上でのルーフトップライブで幕を閉じましたが、このとき彼らはすでに解散の危機を迎えていました。
(最後を飾るルーフトップライブ eiga.comより)
音楽アルバムの発売としては、この映画「レット・イット・ビー」のサントラ盤となったアルバムが最後のアルバムとなりましたが、録音した順番で言えば、その前に発売された「アビイ・ロード」が、彼らがビートルズとしてスタジオで録音した最後のアルバムだったのです。そして、最終アルバムの録音時間が、47分25秒であり、その作品の完成はまさに奇跡でした。
今週は、この「アビイ・ロード・セッション」の前後を緻密な取材によって描き出したドキュメンタリー本を読んでいました。心が打ち震えました。
「ザ・ビートルズ 最後のレコーディング ソリッドステート革命とアビイ・ロード」
(ケネス・ウォマック著 湯田賢司訳 UD BOOKS 2021年)
(「ザ・ビートルズ 最後のレコーディング」amazon.co.jp)
【最後のアルバム「アビイ・ロード」】
ビートルズは、デビュー以来、ジョージ・マーティンのもとでEMIのスタジオでのレコーディングを続けていましたが、ホワイトアルバムからゲット・バック・セッションにおいてはそのスタジオでの録音に問題が生じていました。この本は、その問題からはじまります。その当時EMIスタジオでは、従来から使われていた録音機材に対する技術者たちの思い入れがあり、時代にアップデイトできていませんでした。その機材は、真空管式の音響装置であり、録音トラックも4トラックだったのです。
当時、トランジスタを使用した新式の録音機材を備えたスタジオが登場し、そうしたスタジオでは8トラックでの録音が可能でした。ビートルズも兼ねてから4トラックでの録音に不満を唱えており、録音をEMIスタジオ以外で行うようになっていたのです。もっとも、EMIスタジオが利用できなかったのは、ホワイトアルバムの録音のために長期間ビートルズがスタジオを押さえていたため、他のアーティストがスタジオ待ちとなっており、ゲット・バック・セッションの間は予約が埋まっていたことも大きな要因でした。
ゲット・バック・セッションは主にトゥイッケナムスタジオとアップルスタジオで録音され、おなじみのEMIスタジオは利用されなかったのです。そして、その間、デビュー以来のプロヂューサーであったジョージ・マーティンとリボルバー以来のエンジニア、ジェフ・エメリックはセッションに参加していなかったのです。
ゲット・バック・セッション終了後の1969年4月14日、新たなトランジスタを搭載した8トラックミキサーが設置されたEMIスタジオにジョージ・マーティンとジェフ・エメリックがスタンバイしていました。それは、その2日前、ポールからジョージ・マーティンに、また以前のように4人でアルバムを創りたい、との連絡があったためです。それが、アビイ・ロード・セッションのはじまりでした。そして、そのアルバムは彼らの最後の傑作アルバムとなったのです。
この本には、アビイロードスタジオにトランジスタを使った8トラック機材が据え付けられてから、解散の危機に見舞われていたビートルズがどのようにして最後の傑作アルバムを完成させたか、すべてのドキュメントを綴った貴重な記録なのです。
(アビイロードスタジオ webchrohasu.netより)
そして、新たな音への挑戦は、やはりこの4人に「魔法」をかけたのです。
【アルバムはこうして完成した】
最後のアルバム「アビイ・ロード」には、彼らの新たな姿が記録されました。
まず、ジョージ・ハリソンの作曲才能の開花です。これまでもジョージは、アルバムに曲を提供してきましたが、このアルバムにはA面2曲目のラブソング「Something」とB面オープニングを飾る「Here Comes The Sun」の傑作2曲が含まれています。「Something」は、ビートルズ作品の中で、「Yesterday」に続いて2番目にカバーの数が多い傑作です。また、「Here Comes The Sun」は、ビートルズ213曲のファン投票で数々の名曲をおさえて13位に輝いています。
次に、このアルバムには7分44秒にもなる、ヘヴィなワルツ「I Want You(She’s So Heavy)」が収められています。この曲は、ジョン・レノンがオノ・ヨーコを想って作った曲ですが、8分近い曲の中に歌詞は題名以外2つのフレーズしか入っていないのです。「So bad」と「It’s driving me mad」のフレーズ。その4つのフレーズのみで聞かせてしまう、ジョンの新境地には脱帽でした。しかもこの曲のエンディングはみごとで、突然空に投げ出された気がします。
そして、全面に使用された当時最先端であったモーグシンセサイザーの響き。それはまるで、隠し味のようにすべての曲の魅力を引き出していますが、ロックアルバムに最初に使われたモーグシンセサイザーとして名をはせています。イエローマジックオーケストラのデビューは1978年ですからその先取り感覚にはうならされます。
さらに、なんと言っても最後を飾る16分にもわたるメドレーです。ジョンとポールが作り上げた豊かな世界。心を打つボーカルと鍛え上げられたコーラス、円熟したドラミングとリードギターに心を奪われます。特に「Mean Mr. Mustard」から「The End」に至る9分22秒は、まさにザ・ビートルズのすべてが凝縮されたような奇跡のメドレーです。
(奇跡の「アビイ・ロード」amazon.co.jp)
この本には、ザ・ビートルズはどのようにして新たな自分たちの音楽を創造したのかが余すことなく語られています。しかし、その創造は決して順調に行われたわけではありません。
アルバム曲の最初の録音は、ジョンの「I want You」が録音された1969年2月22日のトライデントスタジオでのセッションから始まりました。しかし、翌月の3月、ポールはリンダと結婚。ジョンもヨーコと結婚しています。この曲は宙に浮いたまま中断しました。そして、4月14日からはじまった「アビイ・ロード セッション」ですが、最初に録音されたのは、シングルカットされた「ジョンとヨーコのバラード」でした。このとき、ジョージとリンゴは別の仕事があり、この曲はジョンとポールだけで録音されたのです。ドラムをたたいたのは、ポールでした。
4月16日には、ジョージ、リンゴもスタジオ入りし、「Something」のセッションが始まります。そして、5月の初めまで、ポール、ジョージの曲を中心にスタジオセッションが進行します。しかし、5月9日、決定的な事件が起こり、バンドは空中分解寸前にまで陥ります。それは、グループのマネジメント契約に対する対立でした。ポール以外の3人はストーンズのマネジメントをしていたアラン・クラインとの契約を望んでおり、アランのうさんくささに気づいていたポールは、リンダの父と兄で構成される弁護士事務所にマネジメントを依頼したかったのです。アランとの契約を迫った3人とポールは、この日に完全に決裂してしまったのです。
プロデューサー、ジョージ・マーティンは、決裂したビートルズは「アビイ・ロード・セッション」を続けることができないとあきらめていました。しかし、事件から1ヶ月後の6月中旬、ジョージ・マーティンのもとにポールから連絡があり、7月からアルバム録音を再開したいというのです。マーティンは改めてスタジオの確保に奔走します。
この再開には、ポールとジョンのアルバムB面を連作メドレーによって完成させるとの新たな野心が原動力となっていたのです。ところが、7月2日、ジョンはヨーコやジュリアンとともに車でむかっていたスコットランド北部で大きな事故を起こし、入院するという大事件が起こります。ジョンがスタジオに復帰するまで、他のメンバーはポール、ジョージ、リンゴが作った曲のセッションを録音することになります。ジョージ・マーティンは、ジョンが復帰後に果たして4人はもめごともなくセッションを完了することができるのか、不安を抱えたまま録音に臨んでいました。
そして、7月9日。満身創痍のジョンとヨーコ、そして絶対安静と告げられた妊娠中のヨーコとジョンのために運び込まれた豪華なダブルベットとともにビートルズのセッションは再会したのです。果たして、数々の問題を抱えたかつてのファブ・フォーはどのようにして傑作「アビイ・ロード」を完成させることができたのか。鍵を握ったのはジョンの「Come Together」でした。
その感動さえ覚えるセッションの様子は、ぜひともこの本で味わってください。
「She Came In Through The Bathroom Window」で窓から入ってきたのは誰だったのか。「Polythene Pan」のPanとは何のことなのか。様々な謎が語られていきます。そして、最後の「The End」において、ドラムソロに絶対拒否を続けていたリンゴがたたいた唯一無二のドラムソロ。さらに、ジョンとポールとジョージによる息詰まるようなギターインプロビゼージョン合戦はどのように行われたのか、このくだりを読んだときには、不覚にも涙が出そうになりました。
ザ・ビートルズは、やはりひとつの奇跡だったのです。
それでは皆さんお元気で、またお会いします。
〓今回も最後までお付き合いありがとうございます。
にほんブログ村⇒プログの励み、もうワンクリック応援宜しくお願いします。