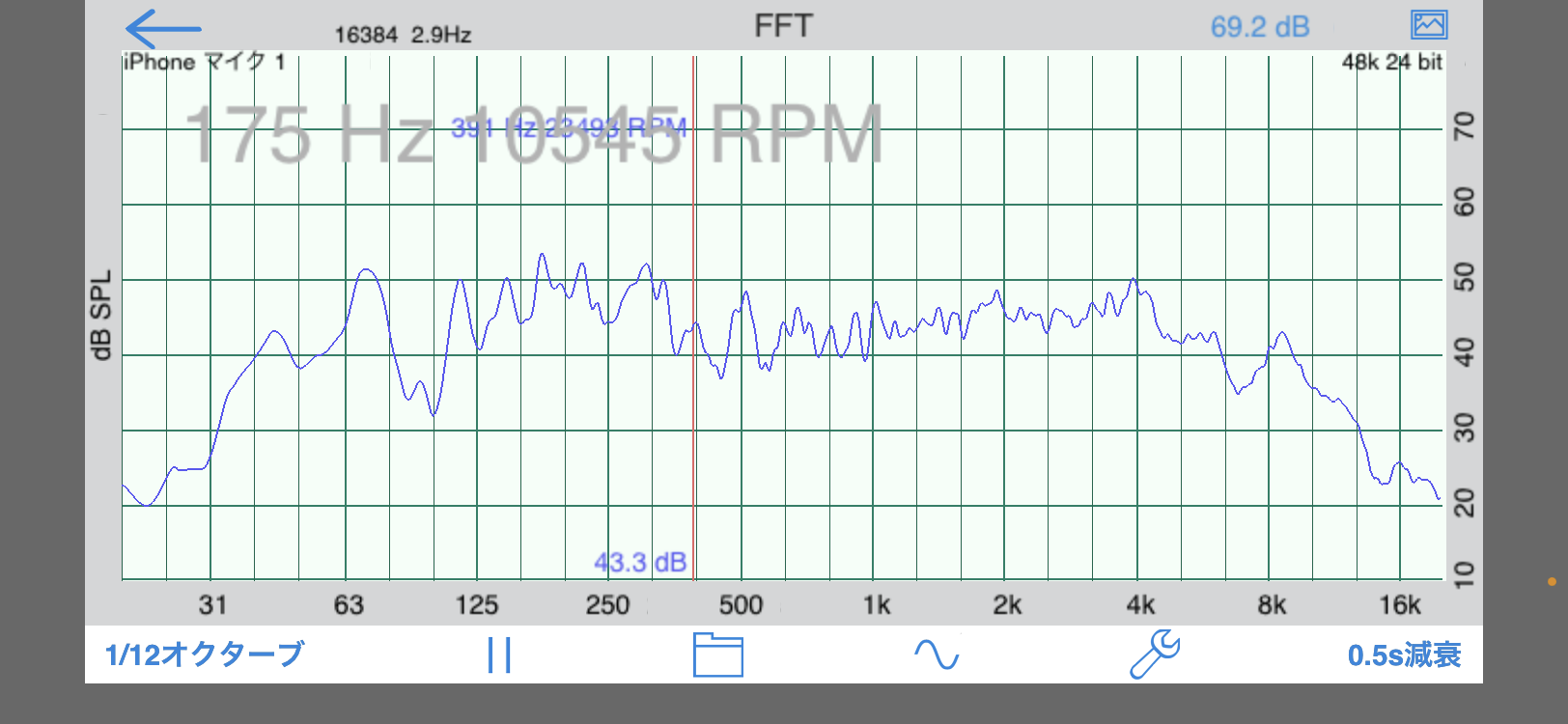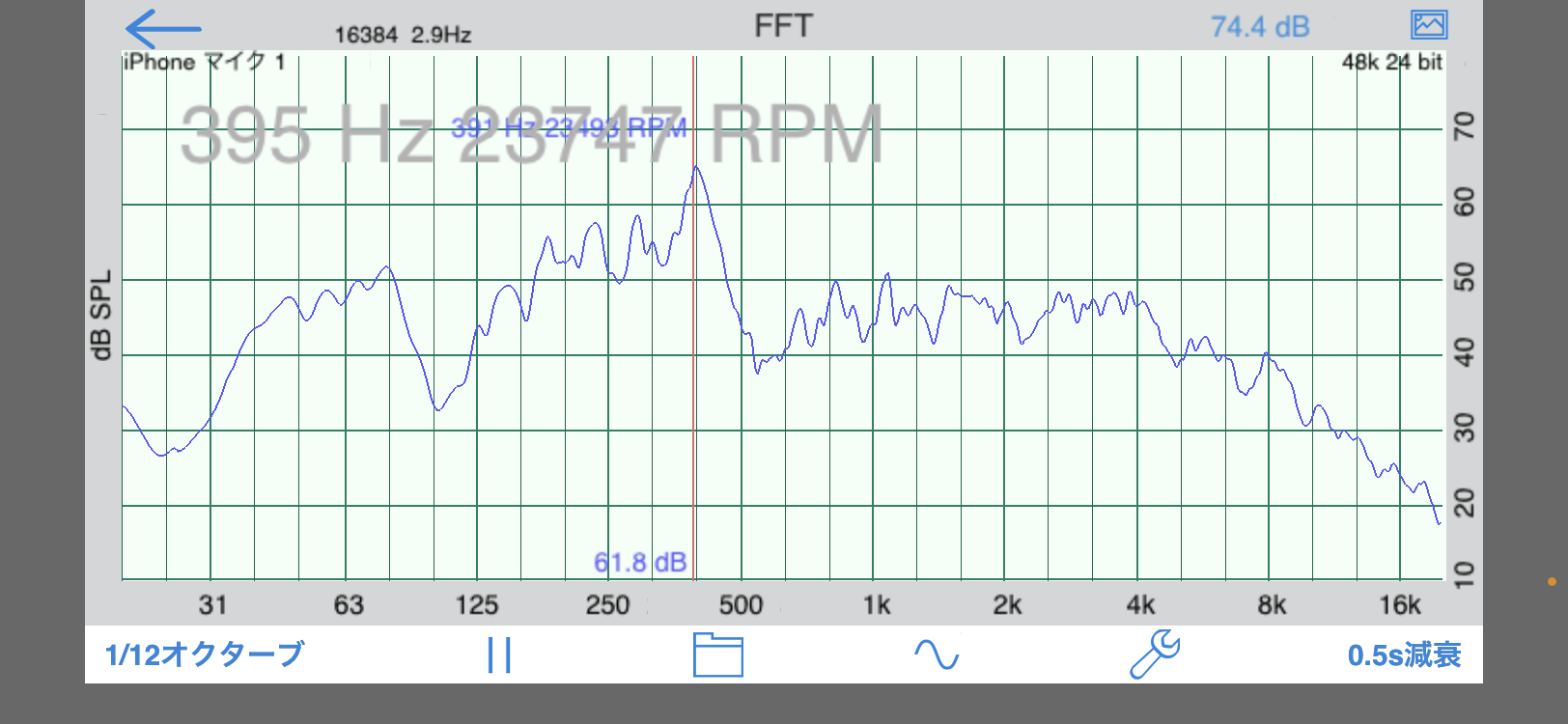厳しい冬もまもなく終わりますね。
 この図は以前に載せた私のTSアームの軸受け部の構造です。
この図は以前に載せた私のTSアームの軸受け部の構造です。軸は図A点の様に鋭利な針のようになっていて、それに擂鉢状の軸受けを被せた構造をしています。
アーム先端は上下、左右とも非常に感度がよくなり、またガタツキも無くせるので、この構造を採用しています。
軸の材質はステンレスSUS304を使っていますが、シェル交換時など強い力でコネクターを締めるとアーム軸の先端に力がかかり曲ってしまう事があります。
 軸先端をよくみると斜めにカットしてある様にみえます。この程度ではあまり音質には問題はありませんが、頻繁にカートリッジを交換をして強くシェルコネクターを締め付ける方はもっと曲ってくるとアームの動作に影響が出てくる可能性があります。
軸先端をよくみると斜めにカットしてある様にみえます。この程度ではあまり音質には問題はありませんが、頻繁にカートリッジを交換をして強くシェルコネクターを締め付ける方はもっと曲ってくるとアームの動作に影響が出てくる可能性があります。さて、先端が曲らない様にもっと硬度の高い材質に交換すれば問題は解決しますので、以前に金属で最も硬いタングステンで軸を作って交換した事があります。硬いので「音質も鮮明になり問題も解決」と言いたいところですが、どうも聴いていて音質が硬くて厳しく疲れてしまうのです。この体験から違う材質で幾つかアーム軸を作って聴いてみようか?と思っていたのです。
 左からステンレスSUS304(硬度187)、ハイス鋼(722)、純チタン(150前後)、64チタン合金(280)です。ちなみにタングステン合金は(3430)です。
左からステンレスSUS304(硬度187)、ハイス鋼(722)、純チタン(150前後)、64チタン合金(280)です。ちなみにタングステン合金は(3430)です。これらの音を聴いてみて分かった事は、硬度が高いほと音も硬い(厳しい)という事です。なのでステンレスSUS304で音質には問題が無いと言う事です。金属としては柔らかい(なまくら)ほうが音質的にも優しい音が出る様です。しかし、軸受けなので銅やアルミの様な金属は柔らかすぎて使えません。
64チタンは硬度も高く、今までの経験で音質にも優れているので期待したのですが、やはり神経質な所がみられました。
この中で一番硬度が低い純チタンですが、柔らか過ぎて先端を尖らす事ができませんでした。

しかし、経験から音質的に優れている金属ですので、何とか軸受けにしてみたいと思って、先端に1.2mmの工具鋼を圧入してから尖らす加工をしてみています。
これが、音質的にも厳しい音が出ないで、先端が曲りにくいという良い結果となりました。異種金蔵を組合わせた事が良かったのかもしれません。
こう考えるとステンレスSUS304の先端だけ焼入れすれば良さそうですが、残念ながら焼入れは出来ない金属です。
ステンレスで焼入れできるのはSUS440系ですので、今後このステンレスも検証してみたいと思っています。
私は軸先端はミクロ的にみると極細になっていますので、針先がレコードに引張られた振動がアーム軸に直接働きますので
金属固有の共振があるのではないか?と推測していますが如何でしょうか?