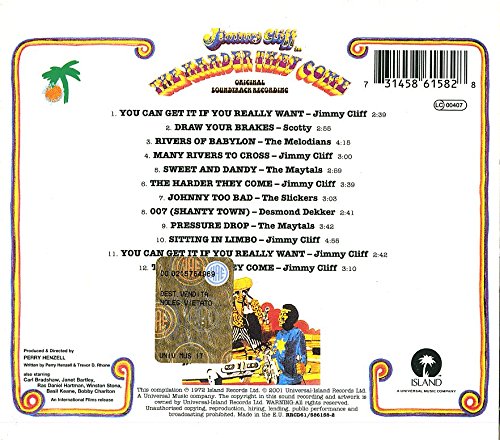レゲエの伝道師、そして広々とした海のような
“祈りの声” が胸にせまってきた。
Jimmy Cliff – “Many Rivers to Cross”

ジミー・クリフを偲び、映画
『ハーダー・ゼイ・カム』(1972/日本公開78年)
を思い返す。
そしてサントラの名曲
“Many Rivers to Cross(遥かなる河)” を上げたい。
70年代、レゲエという音楽に初めて触れたあのころ。
ロックより衝撃だった。ぶんじゃかと独特に揺れるリズム。
ソフトで優しい音なのに、権力や搾取と向き合う鋭さもある。
10代の自分に芽生えた“社会への疑問”を、
そっとなぞってくれるような歌。
ソフトなバラードのはずなのに、ただの異国の歌ではなく、
むしろ 心を照らすように思えた。
Many Rivers to Cross(遥かなる河)
Many Rivers to Cross — 渡らなければならない川がまだいくつもある
But I can’t seem to find my way over — でも渡る道が見つからない
Wandering, I am lost — さまよい、道を失う
10代のときに聴いた歌が、60代になった今も変わらない。
やっぱりこれは、“本当のこと”を歌う歌 だからだと思う。
“Many Rivers to Cross” は、人の普遍性を教えてくれる歌だ。
■ 皆さんはレゲエを、どんな時期に知りましたか?
私のレゲエとの最初の接点は、
クラプトンの「アイ・ショット・ザ・シェリフ」。
そして NHK『ヤング・ミュージック・ショー』で放送された
ボブ・マーリー&ウェイラーズ(1978)の衝撃。
世界にこんな“本物の歌”があるのか、と驚いた。
大学受験勉強より洋楽とレゲエのほうに頭が向いてしまい、
そこから本格的にレゲエを聴き始めた。
そして、ボブ・マーリーより先に世界へ出ていた
ジミー・クリフの存在 を知る。
日本公演はクリフが78年、マーリーが79年。
どちらも行っていない。
今でも悔やんでいる。観たかった、本当に。
この動画クリフがアコギ一本で歌う、素晴らしい!
音楽の才、声の震え、そのすべてが“祈り”に近い。
ただただ “みんなのために” 歌っている感じがする。
■ 歳を重ねて分かる “渡らなければならない川”
「渡らなければならない川がまだいくつもある」
この1行に、人生の重さと希望がすべて入っている。
若いころは“越えられない壁の歌”だと思っていた。
でも今聴くと、
「それでも歩き続ける人間の意志」 の歌に聴こえる。
人には突然“川”が現れる。
仕事、人間関係、家族、自分自身——。
その川の前で立ちすくむ前にこそ、
ジミー・クリフの歌声は、ひときわ温かい。
■ 映画『ハーダー・ゼイ・カム』について
この映画は、レゲエとジャマイカを世界に知らしめた
記念碑的作品。
サントラの曲はどれも存在感がある。
反骨、貧困、ジャマイカの日常のリアリティ。
そんなテーマを背負いながら、
どこか可笑しく、さびしく、
どこまでも 人そのもの を描いていた。
と云うことでおまけも同サントラのから主題で
落ち込んだ時によく聴いた歌で、
「危機や困難は迫ってくるけれど、
いつも困難なら平常だよ」と
言われているようで、いつも元気をもらった
Jimmy Cliff – The Harder They Come
ジミー・クリフに感謝!!!
にほんブログ村
押していただき感謝です。m(_ _ )m