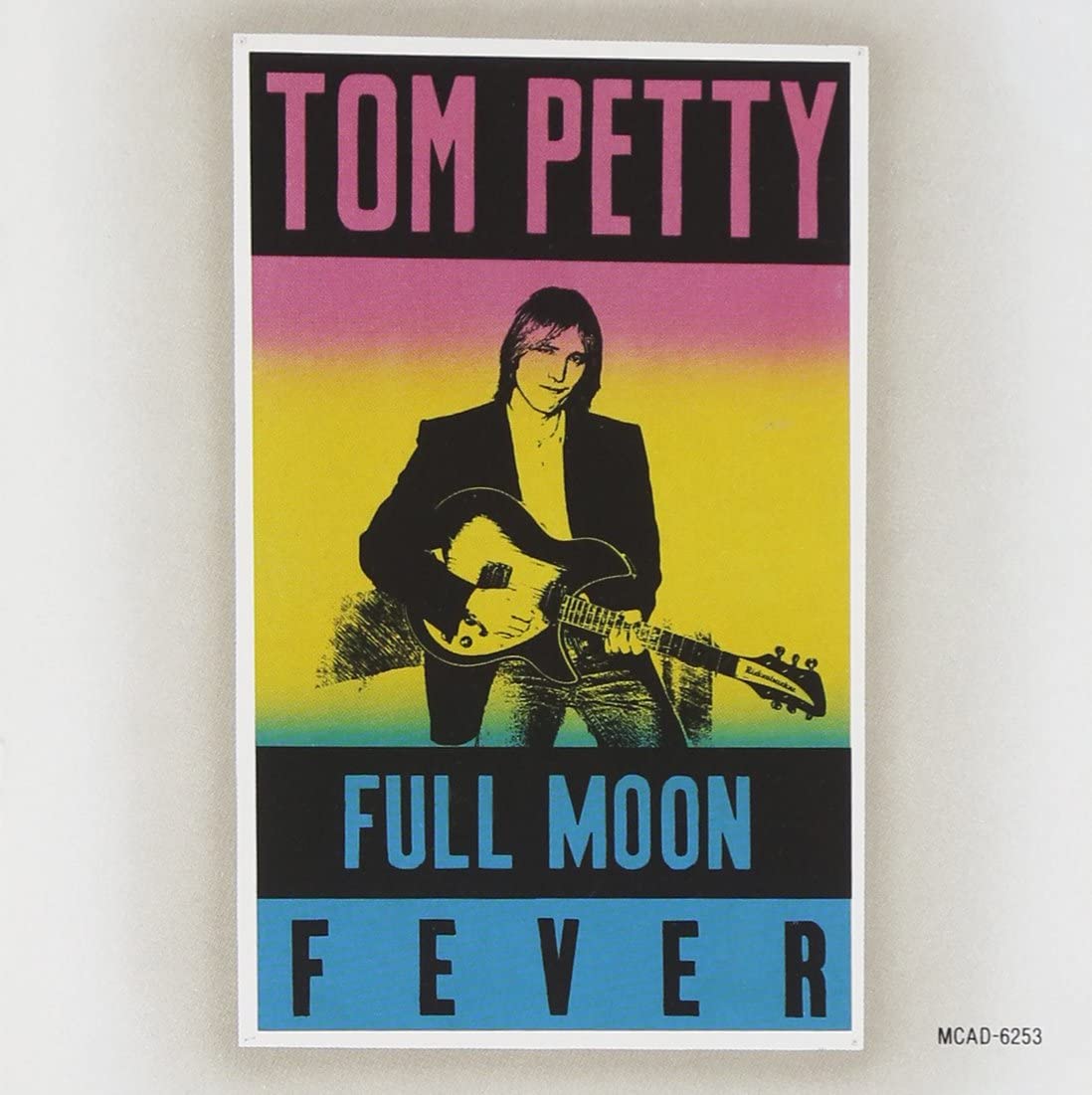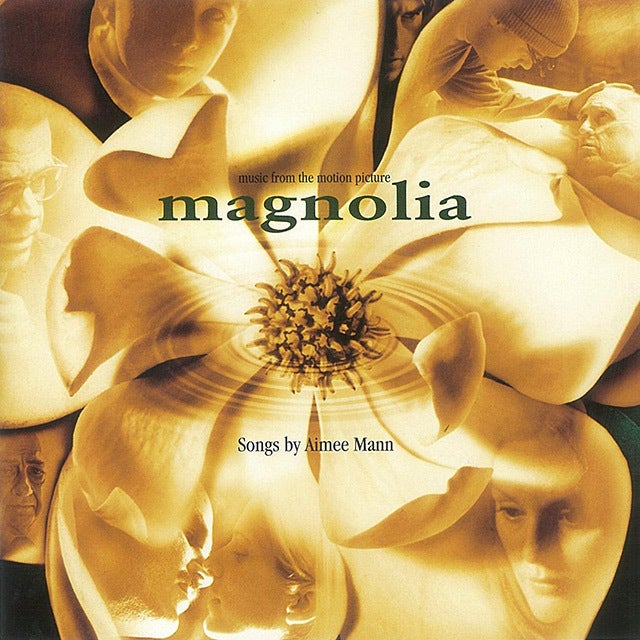NYパンクのデッド・ボーイズはセックス・ピストルズ同様に短命ですが、小生的に大好き。
デッド・ボーイズの存在を知ったのは上京して80年代になってから、その中心メンバーのボーカル、スティーブ・ベイターがUKとの交流!
ロンドンパンクのダムド初期のギタリストのブライアン・ジェイムス、シャム69のベースのデイヴ・トレガンナ、ドラムはレインコーツ・バラクーダズのニックターナーとバンドを組んだが、ローズ・オブ・ザ・ニュー・チャーチ。
一応、英米混合パンク・バンド、グンバツに売れ筋の元バンドではありませんが、そもそもパンクはメインストリームでなく、カウンターソングですから、パンク好きにはヘビィな存在感。

小生が気がついたのは、デビューより少し遅れて84年、その頃社会人になるのですが、映画会社に入ったのに他部門に配属、自暴自棄に…夜中夜中、新宿夜遊び徘徊、クラブでローズ・オブ・ザ・ニュー・チャーチを知るわけで…
レコード、輸入盤を探しに六本木に。でも今は手元に無い(笑)この頃、アパートの部屋鍵かけず、近所の高校生・大学生のたまり場。
本人は家にも帰らない遊ぼうほうけて、最後は肺炎で医者に入院しないと「死ぬ」と言われ、その場で緊急入院させられた頃。
このバンド、懐かしいのと、やるせないセンチが交錯する、いまだに。
NYのニューヨークドルーズのジョニー・サンダースのソロアルバム『ソー・アローン』もロンドン録音でUK系ミュージシャン達のヘルプありでしたが、NYミュージシャンとUKと交わるといい塩梅にロック、パンクする。
この『The Lords of the New Church 』アルバムは小生にとって、捨て曲なし。この次作83年『Is Nothing Sacred? 』は幾分POP化、ダンスミュージックでも好きでしたが。
やっぱり1stが鮮烈です!!
と云うわけでおまけは同アルバムの曲で
The Lords of the New Church - New Church
にほんブログ村
押していただき感謝です。m(_ _ )m