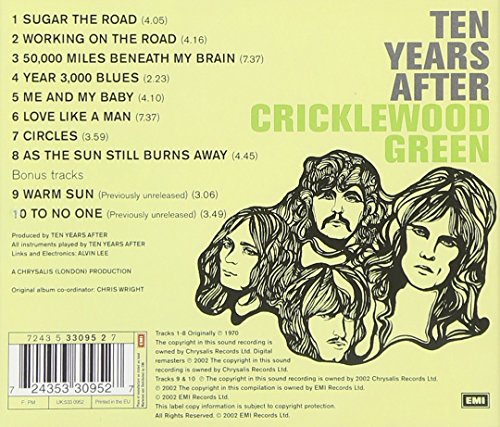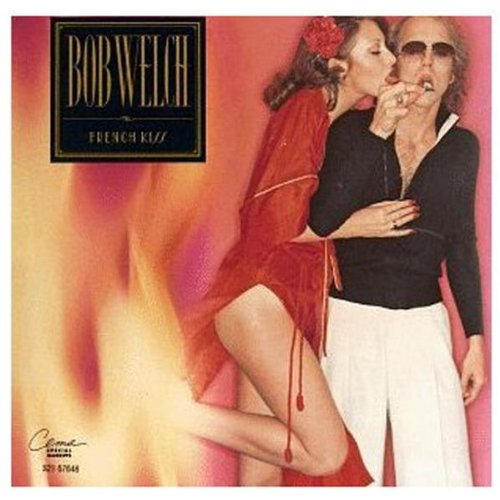ダリル・ホール&ジョン・オーツの「Family Man(ファミリー・マン)」は、1982年リリースのアルバム『H2O』の収録曲ですね。ディスコとソウルが交差した黄金時代の一枚になると思う。でも…
70年代後半から80年代にわたる、米国を代表するデュオ、ダリル・ホール&ジョン・オーツ。アルバム名は「Hall & Oates(H&O)」と化学式の水「H₂O」を掛け合わせたネーミング。当時はアルバムジャケットがいまいちと思っていたのはよく覚えている(笑)
80年代に入るとディスコミュージック、ダンスミュージックを意識したホール&オーツ。
小生の極小のデートの思い出では、女の子と同伴で行けたディスコでは、このアルバムの「Maneater(マンイーター)」は強力で、よくかかっていた。女の子は「食べられなかった」けれど(笑)。他にも「Kiss on My List」「Private Eyes」「Out of Touch」も懐かしい。
70年代のブルーアンドソウルは今も心地よいのですが、80年代のダンスとポップの融合した曲風が流行りだし、ガチガチのソウル出のダンスミュージックより、シックなどよりも、ホール&オーツのほうが親しみやすかった。
リリース年:1982年
収録アルバム:H2O(H2O)
初版(US)発売年:1982年 / 日本盤:1982年(RVC/RCA)
位置づけ:通算11枚目のスタジオ・アルバム。前作『Private Eyes』の成功を引き継ぎ、セルフ・プロデュースによって完成した黄金時代の代表作。
「Family Man」という曲
「Family Man」は、英国プログレの巨匠マイク・オールドフィールドが1982年に発表した楽曲を、わずか数ヶ月という異例の速さでカバーした一曲。個人的には、ホール&オーツ版のほうが好みだ。
R&Bやソウルのルーツを保ちつつ、ニュー・ウェイヴへの感度も示したスタイルが最もよく表れているのが、このアルバムではこの曲かもしれない。
誘惑に抗う男の葛藤を描いた歌詞と思うが、ダリルの才気あるボーカルが彼は単なる「ポップ・スター」ではなく、ソウル・シンガーであることを証明している。
『H2O』について
でも、今聴くとファンの方、ごめんなさいね。批判でなく、分析ね。40年以上前のアルバムなのに(笑)、あれだけ好きだった作品にも、違和感に気づく。
70年代のディスコが「バンドによるグルーヴ」だったのに対し、「プログラミングによるダンス化」が始まった頃と思う。シンセが突き刺し、中音域が落ちて、スカスカしたサウンドで、FMラジオやカーステレオで派手に鳴るよう設計されていたと思う。音楽が機器や聴く側に合わせる必要のある曲風でもあったかな、と思った。
これが顕著に表れるのが次作1984年の『Big Bam Boom(ビッグ・バム・ブーム)』だと思う。当時はカッコいいと疑いなく思っていたが。
なぜかスマホに勝手に入る音楽ニュースでホール&オーツの裁判沙汰と曖昧な解散表明を見て、上りにしては寂しいと思う気持ちも加味して、久しぶりに好きだったアルバムに、ちと厳しい目を向けたかもしれないが…
ということで、おまけは同アルバムから、ブルーアンドソウルの曲あります。
Daryl Hall & John Oates-Open All Night
4500頁、15年の熱量を、今の視点で削り出す。
【再編集2026】プロジェクト始動。
ロックはここから始まった
にほんブログ村 押していただき感謝です。m(_ _ )m