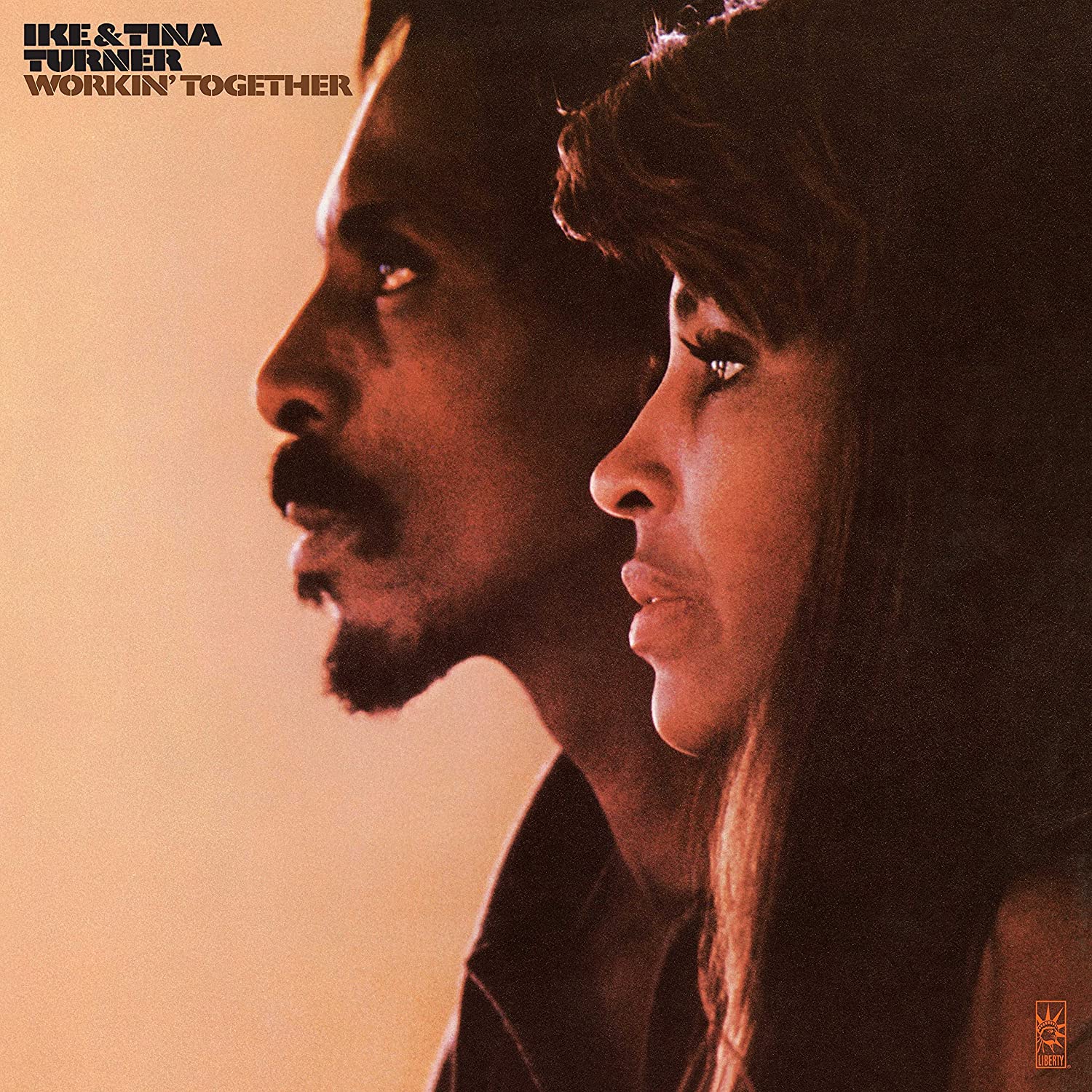ブリティッシュロック、小生的には80年代半ば、興味はかなり失せました、ポリス解散が大きかった。
で、90年代になって30歳代になるとブリットポップなるものには???
当時、これは正直な気持ち、モッズ・グラム・ハード・プログレ・パンク・ニューウェイブがあって、いきなりPOPかと!
いっしょに働く、20代社員やバイトの学生さん達では、オアシスなど神格化で…はあああとため息でしたが、今はオアシス・ブラーも好きですがフォローになって無い(笑)
ここらへんは、前段階でブリティッシュロックのキモ、革新を確定にしたバンド、素直に聴けば、ザ・ストーン・ローゼズ、レディオヘッド、プライマル・スクリームあたりが、起点と、90年代ブリティッシュロックの流れと。

そのザ・ストーン・ローゼズが寡作で、88年1st『The Stone Roses:石と薔薇』とこの『Second Coming:セカンド・カミング』アルバムは2枚だけ。
特に『石と薔薇』はウルトラレベルの評価高、歴代全ブリティッシュロックのアルバム1位 ほんと??と思いますが(笑)
迫力ありでPOPロックでも、爆音で聴くと飛ぶ!トランス状態、ジジイでも久しぶりに聴いたら、なった!
で、さらにハードの評価、小生的にはリズム・ドラム、そしてギターでしょうと思いますが『Second Coming:セカンド・カミング』 ZEPの影響ありのようですが。
基本ハードロック好き、POPロックの激しいモノは好きですし、音色・曲風に創意工夫、70年代ブリティッシュロックをリスペクト、メンバーが60年代生で小生と同世代。
音楽体験が共感、シンクロでするわけでメロディアス、ブリットポップなるモノよりは、今でも自然に聴ける、違和感なしのザ・ストーン・ローゼズです。
と云うことでおまけは同アルバムの好きな曲で
The Stone Roses - Driving South
にほんブログ村
押していただき感謝です。m(_ _ )m