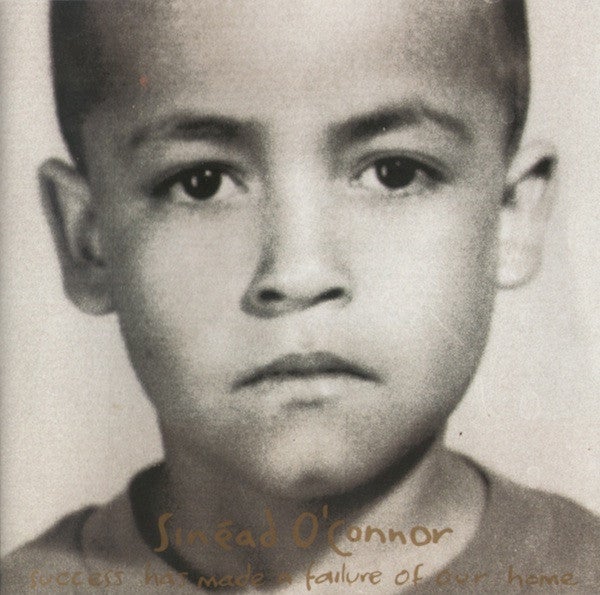「Sax And Violins:サックスとヴァイオリン」は「セックス、バイオレンス」をパロった題で、如何にもトーキングヘッズ。
トーキング・ヘッズの最後アルバムですが、この「Sax And Violins」は、ヴィム・ヴェンダース監督の91年(日本92年)映画『夢の涯てまでも』でのサントラ曲で、この曲の91年録音後に正式解散だったのですね。
当時、この曲はサントラアルバムのみでしたが、トーキング・ヘッズのベスト盤や05年再販盤『ネイキッド』のボーナストラックとしても聴けるようです。
曲は如何にも、これもトーキングヘッズ 無国籍…ワールドミュージック風、ずっと77年1st『サイコ・キラー'77』から、これが新しいのだと我慢して(笑)判ったような顔して、聴かないといけないような雰囲気をずーーーーーと持たせたバンド(笑)
美大系バンドはあるあるで、唯一、誰とも違うが、重要だったと思う、音楽もアートなんで芸術なんで。

90年・93年にNY徘徊、ライブハウスCBGBに通い、トーキング・ヘッズやB52s、ラモーンズ、テレヴィジョン、パティ・スミス、ブロンディ、デッドボーイズ、ジョニー・サンダース&ザ・ハートブレーカーズ、ディクテイターズの残り香は確認したく。
NYでは、トーキング・ヘッズの人気が高いと実感でしたが、その頃は解散、分裂騒ぎでも、親派はいた、注目。デヴィッド・バーンの才、バンドのライブパフォーマンスには、評価ありでしたが。
バーンの才に注目集まり、他のバンドメンバーとアンバラスとバーンの映画がらみで、解散だったと思う。
トーキング・ヘッズは初期はブライアン・イーノのプロディースが多いのですが、この88年『Naked:ネイキッド』はこれもニュー・ウェイヴ育ちには外せないスティーヴ・リリーホワイトがトーキング・ヘッズと共同プロデューサーなんですね。
スティーヴ・リリーホワイトのキラキラサウンドが、少し落ち着き感ありでのクリアなキンキン音で、落ち着きテクノPOP風で、静かロックとして、ようできている。
メンバー間はギクシャクでも、音楽・アルバムには関係なし、これもビートルズから変わらじ。
と云うことでおまけは同アルバムから
Talking Heads - [Nothing But] Flowers
にほんブログ村
押していただき感謝です。m(_ _ )m