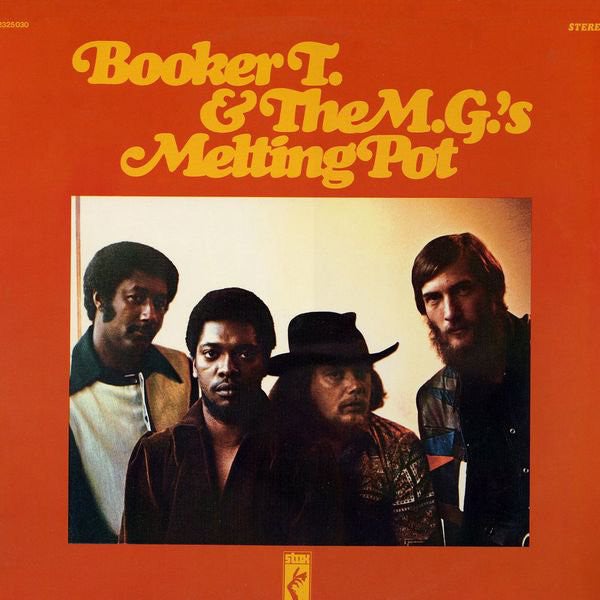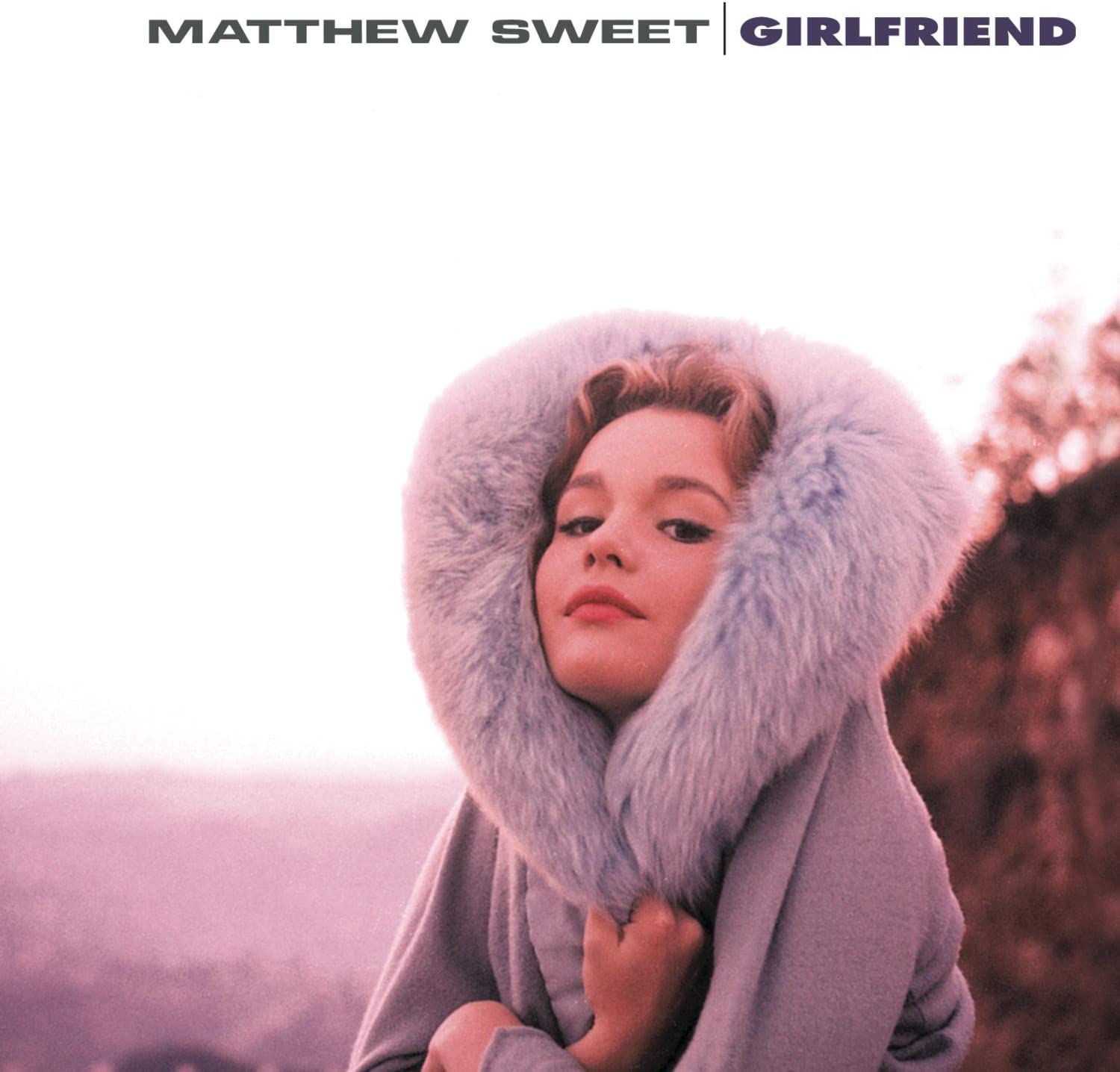2回目のアップですが…
オリンピックは奥方主導の元、TV観戦かなりしてるようで、小生も気なるスポーツ、サッカーとか陸上とかバスケとか空手とか、そしてクライミングは観入ってしまいました。
郷里のヒロイン、野口さん、スポーツクライミング銅メダル、おめでとうございますと素直に思いました。
父が元気な時、散歩で近所の野口さん父と知りありになり、ボルダリング稽古場見せてもらったと言ってのは10数年前の事。
まあ、それに小生自身、ロッククライミングに夢中になった時期がありまして、ロックとロックミュージック・演劇/映画の大学生で勉強なんって皆無。
それなのにスポーツクライミング放送中、講釈しながら解説もどきの奥方に腹立ちで!
小生「クライマーにむかって、何言っての?」
奥方「誰????」真剣に言った、さらに腹立ち(笑)
でも、3種複合の仔細なルール 点数順位これは知らっかった。
北岳バットレス中央稜で落石事故でやめてしまったロッククライミングですが本番では落ちた事は無かったですが、練習ゲレンデ・奥多摩・横須賀市鷹取山では、落ちた………
その感覚がスポーツクライミングTV観戦でよみがえり、足元が抜けるような冷感、40年近く昔の事なのに……と無我夢中で観ている自分に落下感で気づきでした(笑)

登山をやめてしまって数年たって、ヴァンヘイレンを抜けたデイヴィッド・リー・ロスのソロ2作目『Skyscraper:スカイスクレイパー』のアルバムジャケを見た時は、驚きました。
こいつ本格的にクライミングやってるの????と、それでもジャケだけの写真だろうと思っていましたが、PV「Just Like Paradise:まるっきりパラダイス」見て、ほんと驚いきました。
オーバーハング(90度以上の壁・スポーツクライミングはスピード以外全部オーバーハング、これも驚きでした)テープアブミ使ってるし、ヨセミテ(フリークライミング聖地でしたね、このフリークライミングは、70年代後半から日本でも流行りだしました)で撮影している。
おちゃらけのデイヴィッド・リー・ロスと思っていましたが、羨望な思いに。
小生もハーフドーム、エルキャピタン、1000m垂直の岩に挑戦したかった。
ギターにはスティーヴ・ヴァイ も参加のアルバムですが、当時はジャケとPVに驚きのアルバムの印象大。
と云うことでおまけは、おちゃらけのデイヴィッド・リー・ロスとは間違っていなかったと思った、どうしようもない動画で(笑)
Dave’s Short Film-Tokyo Story
にほんブログ村
押していただき感謝です。m(_ _ )m